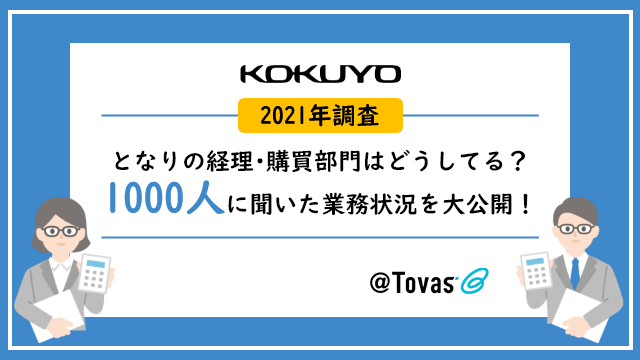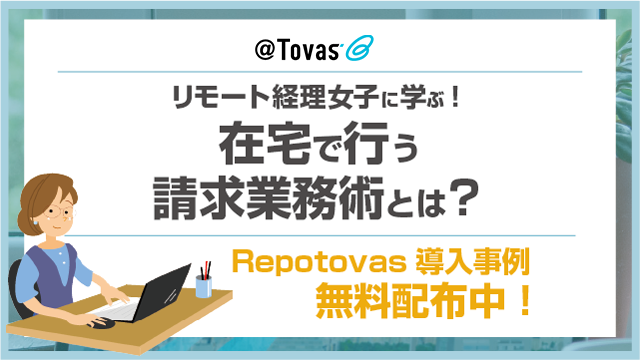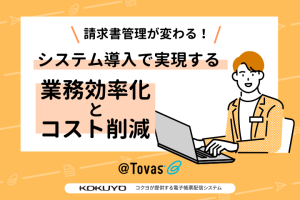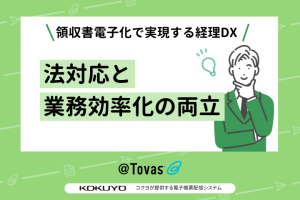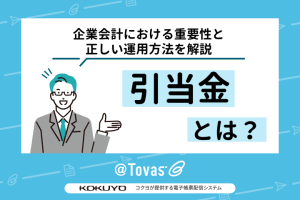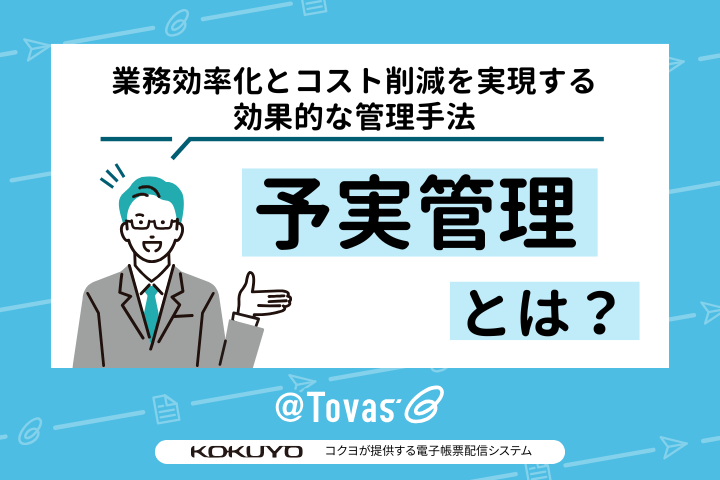
予実管理とは?業務効率化とコスト削減を実現する効果的な管理手法
公開日:2024年12月26日 更新日:2025年3月23日
企業経営において予算と実績を適切に管理し、分析・改善を行う「予実管理」の重要性が、かつてないほど高まっています。2024年は、金融商品取引法の改正や産業競争力強化法の改正など、企業の経営管理に関わる重要な法改正が相次ぎ、より精緻な経営管理が求められる時代となりました。
本記事では、予実管理の基本から具体的な実践方法、システム選定のポイントまで、経営管理の効率化とコスト削減を実現するための手法について詳しく解説します。
予実管理の重要性が増す背景

経営環境の変化と予実管理
予実管理は企業経営の要となる管理手法ですが、近年の法改正や社会環境の変化により、その重要性は従来以上に高まっています。これまでの予実管理は、各部門での個別最適な運用にとどまることが多く、経営環境の変化への迅速な対応が難しいという課題がありました。
法改正による管理体制の強化
2024年4月1日から施行される金融商品取引法等の一部改正では、四半期報告書が廃止され、上場企業の予実管理や情報開示のあり方に大きな変更が求められることとなりました。これに伴い、企業には詳細な経営状況の把握とタイムリーな情報開示が必要となっています。
また、産業競争力強化法の改正では、国内投資の促進やイノベーションの促進に向けた措置が講じられ、企業の投資計画や予算管理においても、より戦略的なアプローチが求められています。このような法改正は、企業の予実管理の重要性をさらに高めることとなりました。
経営の透明性確保への対応
予実管理の重要性が増す背景には、経営の透明性向上への要請も挙げられます。2024年4月からは、労働安全衛生法の改正により、管理監督者の労働時間把握が義務化されました。企業は管理職を含むすべての従業員の労働時間を適切に把握し、人件費の予算管理や労務管理の精度を向上させる必要があります。
さらに、2024年4月1日からは、企業の内部管理に関する新しい基準が改訂され、業務の正確性とセキュリティを高めるためのITシステムの活用が重要とされています。予実管理においても、より安全で効率的な仕組みづくりが求められています。このような変化は、予実管理のデジタル化への対応が不可欠であることを示しています。
そこで次章では、このような環境変化に対応するための予実管理の基本的な考え方と、その具体的な効果について解説します。
予実管理の基本とメリット

予実管理の基本的な考え方
予実管理とは、予算目標を立て、実績と比較・分析することで、経営状況を把握し、改善につなげる管理手法です。経済産業省の産業競争力強化法の改正案でも示されているように、国内企業の競争力強化には、適切な予算管理と実績分析が不可欠とされています。
予実管理の基本となるのは、予算設定から改善活動までの一連のプロセスです。まず、過去の実績をもとに年間予算を立て、それを月ごとに配分していきます。産業競争力強化法の改正案が示すように、特に中堅企業の成長を実現するためには、綿密な投資計画と予算管理が重要です。
実績把握と分析のポイント
実績の把握は、売上、売上原価、販管費、営業外損益の区分ごとに実施します。2024年4月からの労働安全衛生法改正により、管理職を含む全従業員の労働時間把握が義務化されたことも、実績把握の重要性を一層高めています。
把握した実績は予算と比較し、差異が生じている場合はその原因を分析します。金融商品取引法の改正により四半期報告書が廃止されることで、より迅速かつ正確な差異分析の重要性が増しています。分析結果に基づき、必要な対策を実行に移すことで、経営改善のサイクルが確立されます。
予実管理による経営改善効果
予実管理の徹底により、経営判断の精度が向上します。経済産業省が示す産業競争力強化の観点からも、データに基づいた的確な判断の重要性が指摘されています。また、適切な予算管理と実績分析により、無駄な支出の特定と削減が可能となります。
内部統制基準の改訂で示されているように、ITを活用した業務効率化は現代の企業経営において不可欠です。予実管理の仕組みを整備することで、業務プロセスの標準化と効率化が進み、より効果的な経営管理が実現できます。
次章では、これらの効果を最大限に引き出すための、具体的な予実管理の実践方法について解説します。
効果的な予実管理の進め方

予算策定プロセスの確立
予算目標の設定は、予実管理の基盤となる重要なプロセスです。2024年の法改正では、国内企業の投資促進や成長の実現には、適切な予算設定が不可欠とされています。予算目標の設定にあたっては、過去の実績に加えて、業界動向や市場環境の変化も考慮に入れる必要があります。
また、2024年4月からの労働安全衛生法改正により、管理職を含む全従業員の労働時間把握が義務化されたことを踏まえ、人件費予算の精緻な設定も重要となっています。予算は単なる数値目標ではなく、法令順守と経営戦略を結びつける重要な管理ツールとして機能します。
データ収集と分析の効率化
予実管理における実績データの収集と分析は、内部統制基準改訂が示すように、ITを活用した効率的な手法が求められています。実績データは、売上や原価、経費など、各区分で把握する必要がありますが、その収集プロセスを標準化することで、より正確で迅速な分析が可能となります。
金融商品取引法の改正により四半期報告書が廃止され、より機動的な経営状況の把握が必要となる中、データの収集から分析までの一連の流れを効率化することが重要です。特に、予算と実績の差異が生じている項目については、その原因を適切に分析し、必要な対策を講じることで、経営改善につなげることができます。
部門間連携による実効性の向上
予実管理の実効性を高めるためには、部門間の連携が不可欠です。経済産業省が示す産業競争力強化の観点からも、組織全体での情報共有と協力体制の構築が重要となります。経営層と現場の円滑なコミュニケーションを通じて、各部門の予算執行状況を共有し、改善活動を推進していく必要があります。
内部統制基準の改訂では、組織全体でのIT活用や情報セキュリティの確保が強調されています。このような要請に応えながら、統一された管理基準のもとで予実管理を進めることで、より効果的な経営管理が実現できます。
次章では、これらの取り組みをより効率的に進めるための、予実管理システムの選定ポイントについて解説します。
システム選定と活用のポイント

予実管理システムの選択基準
内部統制基準の改訂により、業務プロセス水準でのITの活用と情報システムのセキュリティ確保が重要視されています。予実管理システムの選定においては、このような要請に応えつつ、企業の規模や業務特性に適したものを選ぶ必要があります。
最も基本的な形態としては、エクセルを活用した予実管理があります。予算、実績、達成率の基本項目を設定し、誰でも始めやすい利点がありますが、詳細な分析や他のシステムとのデータ連携には課題が残ります。
一方、クラウド型のシステムは、場所やデバイスに依存せずにアクセスできる利点があります。特に、情報システムのセキュリティ確保が重視される中、データの暗号化やアクセス制御などの機能は重要な選定ポイントとなっています。
システムの機能性と運用性
予実管理システムでは、リアルタイムでのデータ解析機能や過去データとの比較分析機能が重要です。経済産業省の産業競争力強化法改正案が示すように、企業の競争力強化には効率的なシステム運用が不可欠となっています。
さらに、2024年4月からの労働安全衛生法改正による管理監督者の労働時間把握義務化に対応するためにも、人事データとの連携や分析機能は重要な要素となります。システムの導入と運用にかかるコストについても、初期費用、運用保守費用、教育コストなど、総合的な観点から評価する必要があります。
@Tovasによる業務効率化の実現
クラウドベースの配信システムである@Tovasは、場所やデバイスに依存しないアクセスと高度なセキュリティ対策を実現しています。特に@Tovas Master+では、基幹システム改修が不要でのデータ連携が可能となり、導入時の負担を軽減できます。
電子ファイル、FAX、郵送といったマルチチャネルでの配信に対応し、取引先ごとの希望に応じた配信方法を選択できる点も、業務効率化とコスト削減に貢献します。クラウド上での宛先情報管理により、より効率的な運用が可能となっています。
次章では、今後の展望と企業が準備すべき事項について解説します。
今後の展望と準備すべきこと

法制度変更への対応方針
2024年は予実管理に影響を与える重要な法改正が相次いでいます。金融商品取引法の改正による四半期報告書の廃止は、企業の情報開示のあり方を大きく変えることとなりました。これにより、より機動的な経営状況の把握と分析が必要となっています。
また、内部統制基準の改訂により、ITを利用した業務プロセスの管理や情報システムのセキュリティ確保が重要視されています。こうした変化に対応するためには、デジタル技術を活用した予実管理体制の整備が不可欠です。
デジタル化への対応強化
経済産業省の産業競争力強化法改正案が示すように、企業のデジタル化推進は競争力強化の重要な要素となっています。予実管理においても、リアルタイムでのデータ分析やクラウドベースの情報管理、システム間連携の強化が求められています。
特に、2024年4月からの労働安全衛生法改正による管理監督者の労働時間把握義務化に対応するためには、人事データと予実管理システムの連携が重要となります。このような変化に対応できる柔軟なシステム構築が必要です。
組織的な取り組みの推進
予実管理の高度化に向けては、組織全体での取り組みが重要です。内部統制基準の改訂で示されているように、業務プロセスの標準化やセキュリティ確保には、全社的な体制づくりが必要となります。
経済産業省が示す産業競争力強化の方針に沿って、デジタル技術を活用した効率的な管理体制を構築することで、より効果的な予実管理が実現できます。今後は、法制度の変更に適切に対応しながら、組織全体での管理体制の強化を進めていく必要があります。
この記事で解説した予実管理の課題に対して、効率的な解決策をお求めの方は、まず@Tovasに資料請求いただき、具体的な改善方法をご確認ください。システムの選定についてお悩みの際は、専門スタッフが御社の状況に合わせたご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。