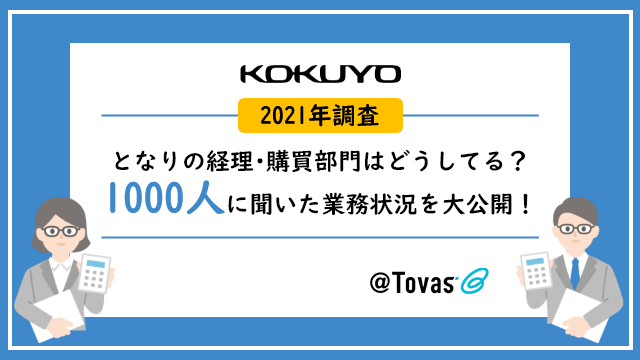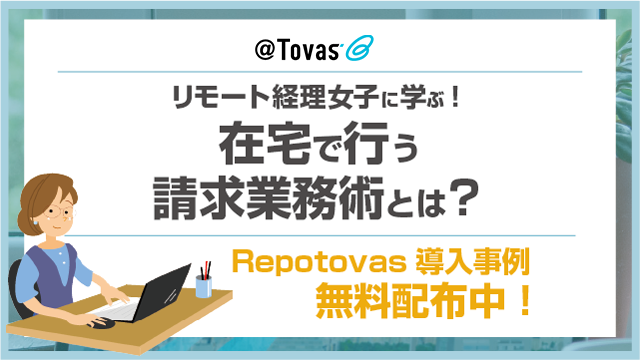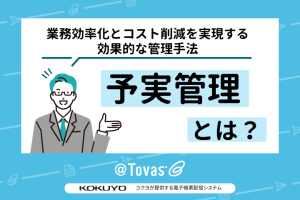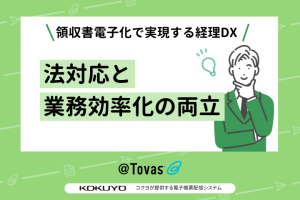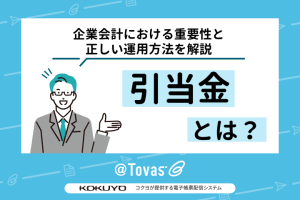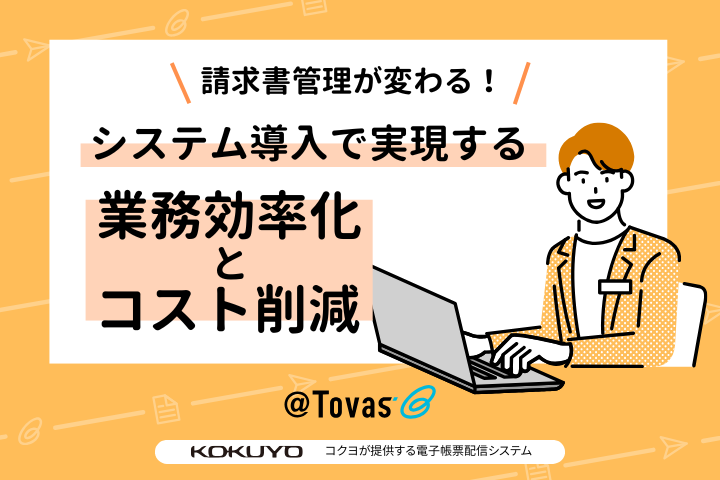
請求書管理が変わる!システム導入で実現する業務効率化とコスト削減
公開日:2024年12月26日 更新日:2025年3月23日
経理部門のデジタル化が進む中、請求書業務だけは紙の運用が根強く残っている企業が少なくありません。しかし、2024年1月からの法改正により、経理業務における電子化対応は待ったなしの状況となりました。本記事では、請求書の電子化と管理システムの選び方について、経理部門の実務担当者の視点から解説します。
TOPICS
2024年1月施行 請求書の電子保存完全義務化への実務対応
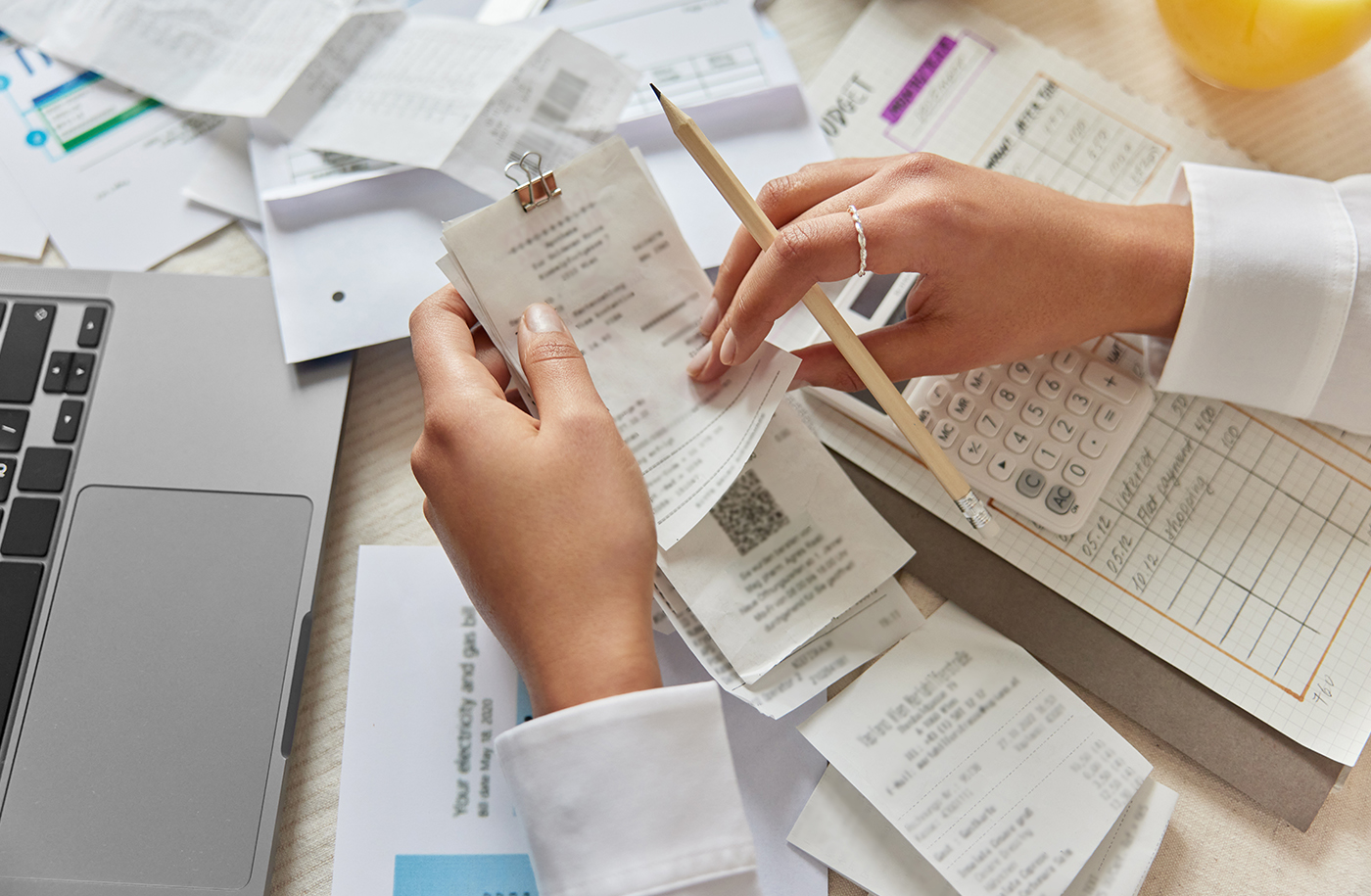 法制度の変更により、請求書の管理方法を見直す必要性が高まっています。電子取引データの保存義務化やインボイス制度への対応など、経理部門は複数の課題に直面しています。
法制度の変更により、請求書の管理方法を見直す必要性が高まっています。電子取引データの保存義務化やインボイス制度への対応など、経理部門は複数の課題に直面しています。
紙の保存では対応できない電子帳簿保存法の改正
電子帳簿保存法の改正に伴い、2024年1月以降、電子的に受け取った請求書データは、電子形式のまま保存することが求められます。2年間の猶予期間が終了し、これまでのように紙に印刷して保存する方法は認められなくなりました。税務調査の際も電子データでの提示が必要となります。
この制度変更により、請求書の受け取りから保管までの業務プロセス全体を見直す必要があります。電子データの保存要件を満たすためには、管理体制の整備が不可欠です。
インボイス制度が変える請求書要件
2023年10月から始まったインボイス制度は、請求書の記載要件を大きく変えています。取引先が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の要件を満たす必要があります。登録番号の記載や、税率ごとの消費税額の明記など、新たな要件への対応が求められています。
令和5年度税制改正では「2割特例」「少額特例」などが設けられましたが、これらは一時的な措置です。本格的な対応を先送りすることはできません。
業務改革としての請求書電子化
法制度への対応だけでなく、働き方改革の観点からも請求書の電子化は重要な課題です。テレワークの普及により、従来の紙の請求書を前提とした業務プロセスでは、柔軟な働き方の実現が困難になっています。
経理部門では、毎月の締め処理や支払い業務において、請求書の確認や承認作業が発生します。場所や時間に縛られない業務プロセスを構築するためには、電子化対応は避けて通れない道となっています。
経理業務の生産性を阻む請求書管理の課題と対応策
 電子帳簿保存法の改正とインボイス制度の本格運用により、請求書の電子化対応が求められる中、経理部門では従来の紙ベースの管理手法に起因する様々な課題が浮き彫りになっています。これらの課題解決は、法令遵守の観点だけでなく、業務効率化の面からも喫緊の対応が必要です。
電子帳簿保存法の改正とインボイス制度の本格運用により、請求書の電子化対応が求められる中、経理部門では従来の紙ベースの管理手法に起因する様々な課題が浮き彫りになっています。これらの課題解決は、法令遵守の観点だけでなく、業務効率化の面からも喫緊の対応が必要です。
経理業務を圧迫する紙の請求書管理
請求書の受領から保管までの一連の業務において、紙の管理は経理担当者に大きな負担を強いています。月末の締め処理時には請求書の仕分けやデータ入力、承認のための社内回覧作業など、定型的な業務に多くの時間が費やされています。
実態調査によれば、紙の請求書管理に費やされる時間は経理担当者の業務時間の約30%を占めているとされています。この作業時間は、取引量の増加に比例して増大する傾向にあり、人的リソースの効率的な活用を妨げる要因となっています。
文書管理コストの増大
法定保存期間に従った紙の請求書保管には、相応の保管スペースが必要となります。インボイス制度への対応で求められる適格請求書の保存要件により、管理すべき文書の量は増加傾向にあります。
都市部のオフィスでは、保管スペースの確保が経費圧迫の要因となっています。保管場所の賃料負担に加え、保管用品や外部倉庫の利用費用など、直接・間接のコストが経理部門の予算を圧迫しています。
法令遵守における正確性の担保
2024年からの電子保存義務化とインボイス制度への対応において、請求書の正確な管理は経理部門の重要な責務となっています。適格請求書の要件として、登録番号の記載や税率区分による消費税額の明記が必要となり、これらの情報を確実に管理することが求められています。
紙の請求書を基盤とした管理体制では、以下のような課題への対応が困難となっています。
登録番号の確認や税率区分の管理においては、手作業による確認作業が発生し、ヒューマンエラーのリスクも無視できません。また、税務調査への対応においても、紙の請求書の検索や提示に時間を要することが懸念されます。
テレワーク環境での業務継続性
働き方改革の進展により、経理業務においてもテレワーク対応が求められています。しかし、紙の請求書に依存した業務プロセスでは、場所や時間に制約が生じ、柔軟な働き方の実現が困難となっています。
在宅勤務時の請求書確認や承認作業、経理部門と他部門との連携、緊急の支払い対応など、様々な場面で業務の遅延が発生するリスクがあります。これらの課題は、企業全体の生産性と従業員の働き方に影響を及ぼしています。
経理業務の効率化を実現するクラウド型請求書管理システム
 経理部門が直面する請求書管理の課題に対して、クラウド型の請求書管理システムが有効な解決策として注目を集めています。従来の紙ベースの運用やオンプレミス型システムと比較して、業務効率の向上と法令遵守の両立が可能となります。
経理部門が直面する請求書管理の課題に対して、クラウド型の請求書管理システムが有効な解決策として注目を集めています。従来の紙ベースの運用やオンプレミス型システムと比較して、業務効率の向上と法令遵守の両立が可能となります。
データ一元管理による業務効率の向上
クラウド型請求書管理システムでは、受領から保管まで一連の作業をデータベース上で完結させることができます。請求書のデータ化と電子的な管理により、手作業による入力作業を大幅に削減できます。
データベースに取り込まれた請求書情報は、取引先や発行日、金額など、様々な条件での検索が可能となります。月次決算時の資料確認や税務調査への対応においても、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を整えることができます。
承認ワークフローの電子化も業務効率化の重要な要素です。システムによる自動通知と承認状況の可視化により、従来の紙の回覧と比較して大幅な時間短縮が実現します。また、承認履歴が自動的に記録されることで、内部統制の強化にも寄与します。
自動化による正確性の向上
請求書管理システムの導入により、手作業に起因するヒューマンエラーを防止することができます。インボイス制度対応において重要となる登録番号の確認や、税率区分に基づく消費税額の計算も、システムが自動的に処理します。
基幹システムとのデータ連携により、会計システムへの仕訳データの転記も自動化が可能です。二重入力の排除により、データの正確性が向上するとともに、転記作業に費やしていた時間を他の業務に振り向けることができます。
取引先ニーズに対応する配信機能
現代の企業間取引では、取引先によって請求書の受取方法が異なることが一般的です。クラウド型システムでは、FAX、メール、郵送など、様々な方法での請求書送付に対応しています。
送付手段の違いにかかわらず、システム上で一元的な管理が可能となります。送付状況や受領確認もデータベース上で管理できるため、取引先からの問い合わせにも迅速な対応が可能となります。
法令要件に準拠したデータ保存
2024年1月からの電子保存義務化に対応するため、システムは電子帳簿保存法が定める要件に準拠したデータ保存機能を備えています。検索機能の確保、改ざん防止措置の実装、タイムスタンプの付与など、法令が求める要件を満たした形でデータを保存します。
データのバックアップ体制も整備されており、自然災害などによるデータ消失のリスクにも対応しています。JIIMA認証を取得したシステムであれば、法令要件への適合性が第三者機関によって確認されているため、安心して利用することができます。
請求書管理システム選定のポイントと評価基準
 クラウド型請求書管理システムの導入は、経理業務の効率化と法令対応の両面で重要な投資となります。システムの選定にあたっては、長期的な運用を見据えた慎重な評価が必要です。
クラウド型請求書管理システムの導入は、経理業務の効率化と法令対応の両面で重要な投資となります。システムの選定にあたっては、長期的な運用を見据えた慎重な評価が必要です。
システム選定の重要評価項目
請求書管理システムの選定において、最も重要となるのがセキュリティと法令対応です。請求書には取引先との機密情報が含まれるため、データの暗号化やアクセス権限の管理機能は必須の要件となります。電子帳簿保存法への対応状況やJIIMA認証の取得有無も、重要な判断基準となります。
システムの操作性も業務効率に直結する要素です。日常的に使用するシステムだけに、直感的なインターフェースと充実した検索機能が求められます。一括処理機能やカスタマイズ性も、業務の効率化に大きく影響します。
導入・運用コストについては、初期費用だけでなく、運用時の様々な費用を総合的に評価する必要があります。月額利用料やデータ移行費用、保守・サポート費用などを含めた総コストを算出し、投資対効果を見極めることが重要です。
基幹システム連携の重要性
請求書管理システムの効果を最大限に引き出すためには、基幹システムとの連携が不可欠です。既存の業務システムとスムーズに連携できるかどうかは、業務効率化の成否を左右する重要な要素となります。
@Tovas Master+のような連携モジュールを活用することで、既存システムを大きく改修することなく連携が可能となります。これにより、データの二重入力を防ぎ、リアルタイムな情報連携を実現できます。
段階的な導入による円滑な移行
システム導入を成功させるためには、段階的なアプローチが効果的です。まず現状業務の可視化と課題抽出を行い、優先度の高い機能から導入を開始します。パイロット運用による効果検証を経て、全社展開へと進めることで、円滑な移行が可能となります。
@Tovasが提供する価値
コクヨが提供する@Tovasは、100年以上の帳票取り扱い実績に基づく専門性を活かしたシステムです。JIIMA認証を取得しており、法令要件への適合性が担保されています。マルチチャネル配信機能により、取引先の要望に応じた柔軟な運用が可能です。
請求書管理システムの導入ステップと準備のポイント
 請求書管理の電子化対応は、2024年1月に迫る法令対応の期限を考慮すると、早期の取り組みが望まれます。ここでは、円滑なシステム導入に向けた具体的な準備とステップについて解説します。
請求書管理の電子化対応は、2024年1月に迫る法令対応の期限を考慮すると、早期の取り組みが望まれます。ここでは、円滑なシステム導入に向けた具体的な準備とステップについて解説します。
導入プロジェクトの進め方
請求書管理システムの導入を成功に導くためには、現状分析から始める必要があります。まず、月間の請求書処理件数や現行の業務フローを可視化し、具体的な課題を明確にします。この分析結果に基づき、電子帳簿保存法とインボイス制度への対応要件を整理することで、システムに求められる機能要件が明確になります。
導入計画の策定においては、社内の関係部門との連携が重要となります。導入スケジュールの設定や必要予算の確保に加え、運用体制の検討も必要です。基幹システムとの連携を予定している場合は、システム部門との早期の調整が不可欠となります。
@Tovasによる課題解決のご提案
経理部門が直面する請求書管理の課題に対して、@Tovasは専門的な知見に基づくソリューションを提供しています。コクヨの持つ帳票業務の専門性を活かし、お客様の課題に最適化された提案が可能です。
以下のような課題をお持ちの企業様に、具体的な解決策をご提案いたします。
電子帳簿保存法の改正に伴う電子保存義務化への対応をご検討の場合、JIIMA認証を取得した@Tovasの機能により、確実な法令対応を実現できます。インボイス制度への対応を含めた請求書管理の効率化をお考えの場合は、電子化による業務プロセスの改善をご提案いたします。
基幹システムと連携した請求書管理の自動化や、テレワーク環境での業務継続性の確保についても、豊富な導入実績に基づく具体的な解決策をご用意しています。ぜひお問い合わせください。