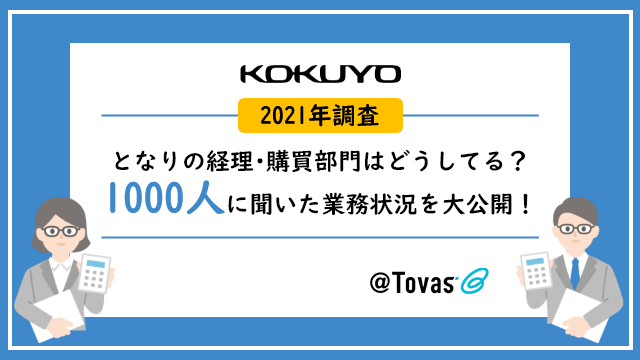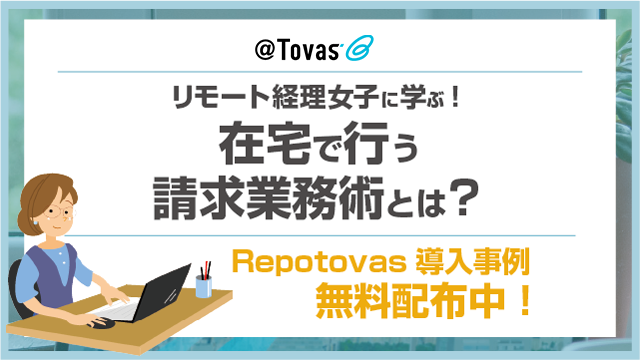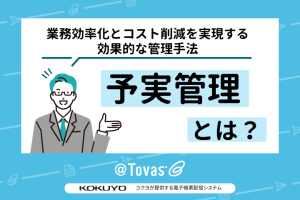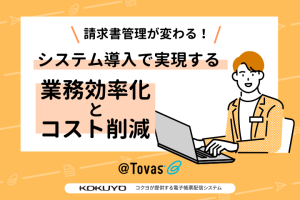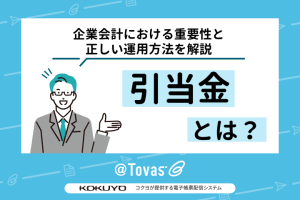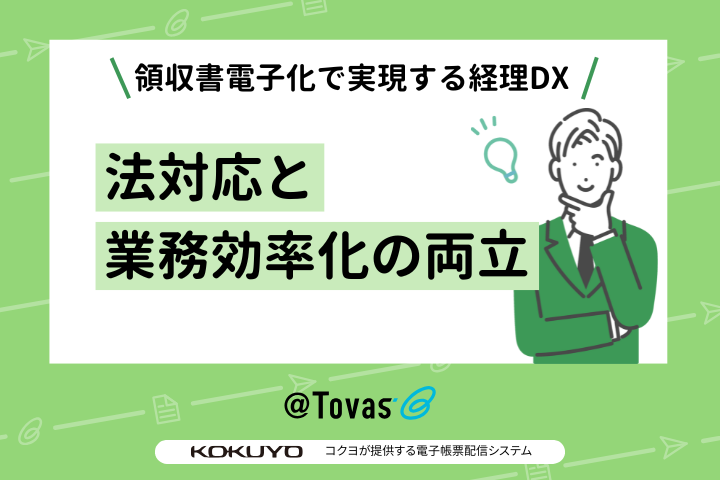
領収書電子化で実現する経理DX 法対応と業務効率化の両立
公開日:2024年12月26日 更新日:2025年3月23日
企業の経理業務において、領収書の管理は基幹的な業務プロセスの一つです。紙の領収書管理には保管スペースの確保や検索の非効率性、紛失リスクなど、数多くの課題が存在します。さらに、2024年1月からの電子帳簿保存法の改正により、電子取引の証憑の電子保存が義務化され、企業における領収書の電子化対応は避けては通れない課題となっています。本記事では、電子帳簿保存法改正への対応と業務効率化の実現方法について解説します。
TOPICS
電子帳簿保存法改正で求められる領収書管理の変革

2024年1月からの電子データ保存義務化の要点
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から、電子取引で受領した請求書等の証憑は、電子データのまま保存することが義務付けられました。この改正は、デジタル社会における企業の経理業務の効率化と、適切な税務管理の実現を目指すものです。従来の宥恕措置は2023年12月31日をもって廃止され、新たな制度へと移行します。
猶予措置の正しい理解と対応
2024年1月1日以降、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合には、条件付きで電子保存の要件(真実性、可視性)を一部満たさない形での保存が認められます。ただし、この猶予措置は電子保存自体の免除ではありません。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
・電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じられること
・電子取引記録の出力書面(整然とした形式・明瞭な状態)の提示または提出が可能であること
この猶予措置は、システムやワークフローの整備が間に合わないなどの事情がある場合を対象としており、資金的な事情を含めた事業者の経営判断についても考慮されます。しかし、システム整備が整っている場合や、単なる経営者の信条のみに基づく場合には適用されません。
経理部門が直面する実務的な課題
電子データ保存の義務化に伴い、経理部門では以下のような実務的な課題への対応が必要となっています。まず、電子データの真正性確保の観点から、改ざん防止や検索機能の確保など、技術的な要件を満たすシステムの選定が求められます。また、データの可読性の定期的な確認や、適切なバックアップ体制の構築も必要です。この状況を踏まえ、次章では領収書の電子化によって実現できる具体的な業務改革について解説します。具体的には、システム導入による業務効率化と、法令要件への対応の両立について説明していきます。
領収書電子化がもたらす業務改革の本質
 前章で解説した電子帳簿保存法の改正と猶予措置は、多くの企業にとって一見すると負担に感じられるかもしれません。しかし、この法改正を契機として、経理業務全体の改革を実現できる機会とも捉えられます。
前章で解説した電子帳簿保存法の改正と猶予措置は、多くの企業にとって一見すると負担に感じられるかもしれません。しかし、この法改正を契機として、経理業務全体の改革を実現できる機会とも捉えられます。
経理業務の効率化とコスト削減の実現
領収書の電子化により、紙の保管スペースやコピー用紙、トナーなどの消耗品費用の削減が可能となります。しかし、より本質的な価値は、経理部門の業務プロセス改革にあります。経済産業省が推進する経費精算システムの導入支援策として、中小企業向けの補助金制度が設立されていることも、この改革を後押しする要因となっています。帳簿や領収書の電子保存は、単なるペーパーレス化ではなく、経理部門全体の業務効率化を実現する基盤となります。ここで重要なのは、現在の猶予措置期間を、将来を見据えた業務改革の準備期間として活用することです。
監査対応における新たな価値創造
日本公認会計士協会から示された電子化された領収書の監査対応ガイドラインでは、データの真正性確認方法やシステムの信頼性評価など、具体的な監査手続きが示されています。これは、単なる法令対応にとどまらず、より効率的で正確な監査体制の構築につながります。コクヨは100年以上にわたる帳票管理の知見を活かし、こうした監査要件に対応したシステムを提供しています。電子データの完全性担保、アクセス権限の管理、バックアップ体制の構築など、具体的なチェックリストに基づいた内部統制の整備を支援します。
テレワーク時代に対応した業務環境の実現
クラウドベースの経費精算システムを導入することで、場所やデバイスに依存しない柔軟な業務遂行が可能となります。これは、現代のテレワーク環境において特に重要な価値を持ちます。ただし、この実現には適切なシステムの選定が不可欠です。次章では、システム選定における重要なポイントについて、具体的に解説していきます。特に、2026年10月から段階的に義務化される電子インボイス制度も見据えた、将来に向けた選定基準について説明します。
領収書電子化の実現手法と具体的な選択のポイント
 前章では、領収書電子化による業務改革の可能性について解説しました。本章では、その実現に向けた具体的な手法と、2024年1月からの法改正を踏まえた選択のポイントについて説明します。
前章では、領収書電子化による業務改革の可能性について解説しました。本章では、その実現に向けた具体的な手法と、2024年1月からの法改正を踏まえた選択のポイントについて説明します。
基幹システムの改修による対応
既存の基幹システムを改修して対応する方法は、現行の業務プロセスを維持できる利点があります。しかし、電子帳簿保存法で定められたデータの完全性確保や、可読性の定期的な確認といった要件への対応には、大規模な改修が必要となる場合があります。また、猶予措置の適用を受けるためには、「電子取引データのダウンロードの求め」や「明瞭な形式での出力」に対応できる機能の実装が必要です。これらの要件を満たすための改修コストと期間を慎重に検討する必要があります。
専用ソフトウェアの導入
電子帳簿保存法対応の専用ソフトウェアを導入する方法は、比較的短期間での対応が可能です。金融庁が2024年7月に発表したクラウド会計ソフトの利用に関する新ガイドラインでは、データセキュリティや監査対応に関する要件が明確化されており、これに準拠したソフトウェアの選定が重要となります。また、経済産業省では中小企業向けの補助金制度を設立しており、システム導入時の初期費用の軽減が可能となっています。
クラウド型経費精算システムの活用
クラウド型の経費精算システムは、導入の容易さと運用の柔軟性を両立する選択肢です。多要素認証の標準搭載、エンドツーエンドの暗号化など、最新のセキュリティ技術が実装されており、特に中小企業向けのシステムでもエンタープライズレベルのセキュリティ機能が利用可能です。さらに、2024年11月に経済産業省から発表された国際標準規格への対応も進んでおり、グローバルな経費精算業務の効率化も視野に入れた選択が可能です。
導入方式の比較検討ポイント
各方式の選定にあたっては、以下の観点からの慎重な検討が必要です。まず、猶予措置の適用要件を満たすための機能の有無を確認します。次に、2026年10月からの電子インボイス制度への対応を見据えた拡張性を評価します。さらに、既存の業務プロセスとの親和性や、社内の受け入れ態勢についても考慮が必要です。次章では、これらの選択肢から最適なシステムを選定するための具体的な評価基準について解説します。
領収書電子化システムの選定基準と評価のポイント
 前章で解説した各実現手法の中から、自社に最適なシステムを選定するためには、複数の観点からの慎重な評価が必要です。ここでは具体的な選定基準について解説します。
前章で解説した各実現手法の中から、自社に最適なシステムを選定するためには、複数の観点からの慎重な評価が必要です。ここでは具体的な選定基準について解説します。
法令要件への適合性評価
電子帳簿保存法の要件への対応を評価する際は、以下の点について確認が必要です。まず、データの真正性を確保するための技術的要件として、改ざん防止機能や検索機能の実装状況を確認します。特に、2024年1月からの法改正に伴う猶予措置を活用する場合でも、将来的な完全対応を見据えた機能の実装ロードマップが明確になっているかどうかが重要です。また、電子データの保存要件として、可読性の確保やバックアップ体制の構築状況、アクセス権限の管理機能などについても詳細な確認が必要です。
セキュリティ体制の評価
クラウド型経費精算システムのセキュリティ評価では、多要素認証やエンドツーエンドの暗号化などの基本機能に加え、AIを活用した不正検知機能の有無も確認します。特に、金融庁が2024年7月に発表した新ガイドラインで示されたセキュリティ要件への対応状況は、重要な評価ポイントとなります。
既存システムとの連携性評価
基幹システムとの連携において重要なのは、データ連携の自動化レベルです。コクヨの専門チームは、既存システム環境を活かした段階的な導入アプローチを推奨しています。これにより、業務の混乱を最小限に抑えながら、確実なシステム移行が可能となります。
総所有コストの評価
システムの導入・運用コストは、以下の要素を総合的に評価する必要があります。初期導入費用と月額運用コストの構成を確認し、経済産業省の補助金制度の活用可能性を検討します。特に中小企業向けには、段階的な導入による投資の平準化も有効な選択肢となります。
将来的な拡張性の評価
国際標準規格への対応状況や、2023年10月から開始されているインボイス制度への対応状況を確認します。特に、電子インボイスからデジタルインボイスへの移行を視野に入れている場合は、Peppolなどの国際標準規格への準拠が重要な評価基準となります。次章では、これらの評価基準に基づいた具体的な導入ステップについて解説します。
領収書電子化で実現する経理業務の未来像
 前章までで解説してきた領収書の電子化は、単なる法対応にとどまらない、経理業務全体の改革機会となります。特に、既に開始されているインボイス制度への対応と合わせて、包括的な業務改革を実現することが可能です。
前章までで解説してきた領収書の電子化は、単なる法対応にとどまらない、経理業務全体の改革機会となります。特に、既に開始されているインボイス制度への対応と合わせて、包括的な業務改革を実現することが可能です。
電子化による業務改革の実現ステップ
2024年1月からの電子帳簿保存法改正への対応は、以下のような段階的なアプローチで進めることをお勧めします。まず、猶予措置の申請要件を満たす最小限の対応を行います。具体的には、電子取引データのダウンロードや、明瞭な形式での出力機能を確保します。この段階で、コクヨの100年以上にわたる帳票管理の知見を活かした基本的な電子化体制を整えることができます。次に、2023年10月から開始されているインボイス制度に対応した電子インボイス対応を検討します。特にPDF形式での電子インボイスから、バックオフィス業務の自動化が可能なデジタルインボイスへの移行も視野に入れた検討が重要です。この際、経済産業省の補助金制度を活用することで、導入コストの軽減が可能です。最後に、基幹システムとの連携や業務プロセスの最適化を進め、経理業務全体の効率化を実現します。
経理業務の将来像と実現される価値
領収書とインボイスの電子化により、以下のような経理業務の変革が実現されます。まず、データの完全性確保や監査対応の効率化により、内部統制の強化が図られます。また、クラウドベースの管理により、テレワーク環境下でも効率的な業務遂行が可能となります。さらに、2024年11月に経済産業省から発表された国際標準規格に準拠することで、グローバルな経費精算業務の効率化も視野に入れることができます。コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、領収書などの帳票書類を電子化して送付できるクラウドサービスです。発行した書類は電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存できるため、領収書をはじめとした書類の電子化に貢献できるでしょう。取引書類の発行・送付にかかる業務効率化を目指している場合は、ぜひご利用ください。