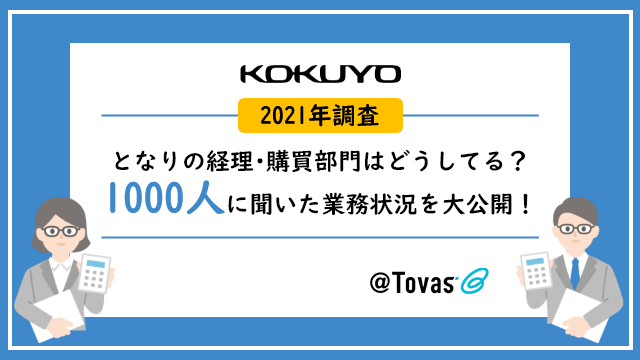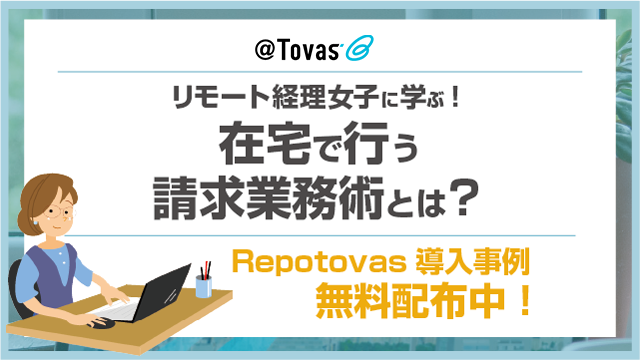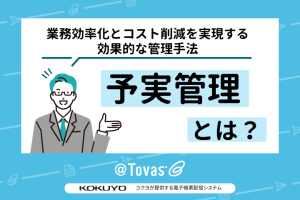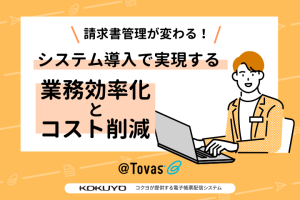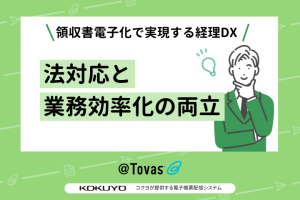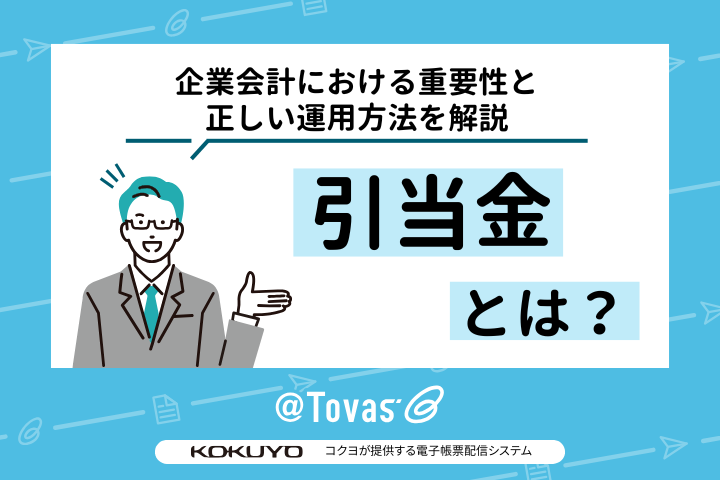
引当金とは?企業会計における重要性と正しい運用方法を解説
公開日:2024年12月26日 更新日:2025年3月23日
引当金は企業会計において不可欠な会計上の仕組みといえます。とりわけ2024年8月の会計基準見直しや、国際会計基準(IFRS)とのコンバージェンスにより、その取り扱いは大きな転換期を迎えているといえるでしょう。
本記事では、引当金を取り巻く環境変化や最新の実務課題について、経理部門の管理者の視点から詳しく解説してまいります。
TOPICS
企業経営における引当金の重要性が高まる背景

会計基準の見直しと実務への影響
2024年8月に示された引当金に関する会計基準の見直しは、企業の経理実務に様々な影響をもたらしています。とりわけ注目すべきと考えられるのが、債務性のない引当金の取り扱いや認識要件の変更です。これらの変更点は、従来の実務との間に看過できない差異をもたらす可能性を秘めています。
加えて、2024年11月にIASBから公表された引当金の会計処理に関する修正提案においては、現在の義務の認識規準が刷新され、引当金の測定方法についても一層の明確化が図られることとなりました。このような国内外における会計基準の変更は、企業の引当金管理の重要性を従来以上に高めているといえるでしょう。
経営リスク管理における引当金の役割
昨今の経営環境下において、適切なリスク管理の必要性は日増しに高まっているといえます。こうした状況を反映し、金融庁が2024年8月に示した金融行政方針においても、金融機関の健全性確保と適切なリスク管理の重要性が強く打ち出されています。
このような流れの中で、引当金は将来の不確実性に備えるための重要な手段として位置づけられています。経営判断に大きな影響を及ぼす見積りの一つとして、経営層からの注目度も一段と高まっているところです。
デジタル化時代における引当金管理の課題
引当金の計上プロセスにおいても、デジタル化対応は避けて通れない課題となっています。金融庁の監督指針においても、デジタル技術を活用した業務効率化の推進が求められており、引当金管理もその例外ではありません。
一方で、こうしたデジタル化の推進にあたっては、システムによる自動化と人的判断の適切なバランス、データの正確性の担保、さらには監査対応の効率化といった新たな課題も浮上してきています。これらの課題に対応していくため、経理部門には従来にも増して高度な専門性とデジタルリテラシーが求められているといえるでしょう。
引当金の基本的な仕組みと種類
 前章では引当金を取り巻く環境変化について述べてまいりました。本章では、そうした変化の中で重要性を増す引当金について、その基本的な仕組みと種類を解説してまいります。
前章では引当金を取り巻く環境変化について述べてまいりました。本章では、そうした変化の中で重要性を増す引当金について、その基本的な仕組みと種類を解説してまいります。
引当金の定義と計上要件
企業会計において、引当金とは将来の特定の支出や損失に備えるために、あらかじめ費用や損失を見積もって計上する会計上の仕組みといえます。2024年8月の会計基準見直しにより、この計上要件についてはより明確な基準が示されることとなりました。
とりわけ注目すべきは、IASBの最新の修正提案において示された引当金の認識要件です。この提案では、現在の義務の認識規準が刷新され、より実務に即した判断基準が示されることとなりました。こうした新しい基準に基づき、経理担当者にはより適切な引当金の計上判断が求められているところです。
主要な引当金の種類と特徴
引当金の種類は多岐にわたりますが、ここでは実務で特に重要となる引当金について解説いたします。
まず、貸倒引当金については、金融庁が2024年の監督指針で示している通り、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分に応じた適切な計上方法の選択が求められています。それぞれの債権区分の特性を十分に理解し、自社の債権実態に即した引当金計上を行うことが肝要です。
さらに、金融機関に目を向けると、2024年5月の銀行法施行規則の改正により、より厳格な引当金の計上基準が設けられることとなりました。特に健全性確保の観点から、リスク管理と密接に連携した引当金管理の実施が強く求められています。
引当金計上における重要な判断ポイント
引当金の計上においては、経営者による適切な判断が不可欠といえます。IASBの修正提案では、将来の不確実性を評価する際の考え方として、経済環境や業界動向を踏まえた合理的な見積りの重要性が示されています。
とりわけ、新しい会計基準で示された測定方法や割引率の使用に関する指針については、慎重な適用が求められるところです。金融庁の監督指針においても、こうした見積りの合理性確保が重要な監督ポイントとして挙げられています。
加えて、内部統制の観点からも、引当金の計上プロセスの文書化や計算根拠の明確化が欠かせません。日本公認会計士協会の指針においても、特別法上の引当金に関しては、法令要件と会計基準の両面からの検証が必要とされています。
引当金に関する最新の実務課題と対応方法
 前章では、引当金の基本的な仕組みと種類について解説してまいりました。本章では、それらを踏まえた上で、実務における具体的な課題と対応方法についてご説明いたします。
前章では、引当金の基本的な仕組みと種類について解説してまいりました。本章では、それらを踏まえた上で、実務における具体的な課題と対応方法についてご説明いたします。
会計基準の改正への実務対応
2024年8月の引当金に関する会計基準の見直しと、11月のIASBによる修正提案を受け、実務対応の見直しが喫緊の課題となっています。とりわけ、現在の義務の認識規準の更新や、引当金の測定方法の明確化については、実務面での対応が急務といえるでしょう。
まず注目すべきは、債務性のない引当金の取り扱いです。IASBの指針に基づけば、より厳密な認識要件の判断が求められることとなります。こうした状況において、将来の不確実性を適切に評価し、合理的な見積りを行うためのプロセス整備が不可欠といえます。
さらに、IASBの修正提案で示された割引率の使用に関する新たな指針への対応も見過ごせません。この対応には、社内の計算プロセスの見直しはもとより、必要に応じたシステム面での対策も視野に入れる必要があるでしょう。
引当金計算の自動化と業務効率化
金融庁が2024年8月に公表した金融行政方針では、金融機関の健全性確保や適切なリスク管理の重要性が強調されています。こうした方針に沿った対応として、引当金計算の自動化とシステム化の推進が求められているところです。
具体的な取り組みとしては、計算プロセスの文書化と標準化が出発点となるでしょう。続いて、システムによる自動計算の導入を検討し、さらには計算根拠の明確化と保存体制の整備へと段階的に進めていくことが望ましいと考えられます。
内部統制における引当金管理の重要性
金融庁による2024年の監督指針の改訂では、引当金に関する監督上の留意点が追加され、より厳格な管理体制の整備が求められることとなりました。これを踏まえ、引当金管理における内部統制の在り方を見直す必要性が生じています。
第一のポイントは、引当金計上の根拠となる見積りの合理性確保です。この実現に向けては、見積りプロセスの文書化や、定期的な見直し体制の構築が有効な手段となるでしょう。
もう一つの重要な視点は、内部統制の実効性確保です。特にシステム化が進展する中で、統制活動の設計・運用状況の評価方法については、従来とは異なる観点からの検討が求められています。
引当金管理における業務改善のポイント
 前章では引当金に関する実務課題と対応方法について説明してまいりました。本章では、それらの課題に対する具体的な業務改善の方向性について解説いたします。
前章では引当金に関する実務課題と対応方法について説明してまいりました。本章では、それらの課題に対する具体的な業務改善の方向性について解説いたします。
引当金計上プロセスの見直し
金融庁が2024年8月に公表した金融行政方針では、引当金を含む会計処理の適切性確保が重要課題として示されています。この方針を踏まえ、引当金計上プロセスの見直しにおいては、いくつかの重要なポイントが浮かび上がってきます。
第一に取り組むべきは、IASBの新たな指針で示された引当金の測定方法に基づく計上プロセスの標準化といえるでしょう。具体的には、見積りの根拠となる基準や計算方法の文書化を徹底することで、継続的な品質確保を図ることが有効と考えられます。
続いて重要となるのが、金融庁の監督指針改訂を受けた引当金計上の判断基準の明確化です。こうした基準の確立により、担当者による判断のばらつきを抑制し、より一貫性のある引当金計上が実現できると考えられます。
システム活用による効率化の実現
金融庁の2024年監督指針では、引当金管理におけるデジタル技術の活用の重要性が指摘されています。システムの効果的な活用に向けては、段階的なアプローチが望ましいといえるでしょう。
まず着手すべきは計算プロセスの自動化による作業効率の向上です。これに続いてデータの一元管理による情報の正確性確保を進め、最終的には承認フローのシステム化による統制強化へと発展させていくことが効果的です。
監査対応を見据えた管理体制の構築
2024年11月に日本公認会計士協会から示された指針では、引当金の監査における重要なポイントが明確化されています。これを踏まえた管理体制の構築が求められているところです。
具体的な取り組みとしては、計上根拠の文書化と保存体制の整備から着手することが推奨されます。その上で定期的な見直しプロセスを確立し、さらには監査証跡の確保に向けた記録管理の強化へと展開していくことが望ましいでしょう。
経理部門の業務最適化に向けた取り組み
金融庁の2024年度金融行政方針では、業務効率化とコンプライアンス強化の両立が求められています。この要請に応えるべく、経理部門の業務最適化では複数の観点からの取り組みが必要となります。
まず重要となるのが業務フローの標準化と文書化です。これに加えて担当者の育成と知識の共有を進め、さらには部門間の連携強化を図ることで、より効果的な業務運営が実現できると考えられます。
これからの引当金管理に求められる取り組み
 前章では具体的な業務改善のポイントについて解説してまいりました。本章では、それらを踏まえた上で、今後の引当金管理において求められる取り組みについて展望したいと思います。
前章では具体的な業務改善のポイントについて解説してまいりました。本章では、それらを踏まえた上で、今後の引当金管理において求められる取り組みについて展望したいと思います。
デジタル化への対応と業務改革
金融庁が2024年度の金融行政方針で示している通り、引当金管理を含む経理業務全般において、デジタル技術の活用による業務改革が重要な課題となっています。
とりわけ、IASBの修正提案で示された新たな測定方法や割引率の使用に関する指針に対応するためには、より高度なシステム活用が不可欠といえるでしょう。具体的には、システムによる自動計算と人的判断を適切に組み合わせることで、より精度の高い引当金管理が実現できると考えられます。
このような変革を進めるにあたっては、データの正確性を確保するための統制活動の確立が重要な鍵を握ります。その上で、継続的な業務プロセスの見直しと改善を図っていくことが望ましいといえます。
なお、こうしたデジタル化の推進においては、クラウド型の帳票管理システムの活用も有効な選択肢の一つとして挙げられます。例えば、コクヨの@Tovasのような帳票Web配信クラウドサービスでは、引当金計算の根拠となる証憑類の管理や基幹システムとの連携機能を活用することで、より正確で効率的な管理体制の構築が期待できます。
経理部門の専門性向上に向けて
金融庁の監督指針改訂を踏まえると、引当金管理における専門性の向上は今後ますます重要性を増すことが予想されます。この課題に対しては、計画的かつ体系的な取り組みが求められるところです。
第一に重要となるのが、会計基準の改正に関する継続的な知識更新です。日本公認会計士協会の指針が示す通り、特別法上の引当金については、法令要件と会計基準の両面への深い理解が不可欠となります。
次に注力すべきは、内部統制の実効性確保に向けた実務能力の向上です。システム化が進展する中、従来の知識に加えて、デジタル技術への理解も求められる時代となってきています。
さらには、部門間連携を促進するためのコミュニケーション能力の強化も欠かせません。引当金管理の質を高めていくためには、経理部門内部の連携はもとより、他部門との協力体制の構築も重要といえるでしょう。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、帳票書類を電子化してWeb上での送信ができるため、経理部門の業務効率化に役立ちます。郵送やFAXでの送信もできるため、取引先に応じて送付方法を選べます。経理DXの実現に向けて、ぜひ導入をご検討ください。