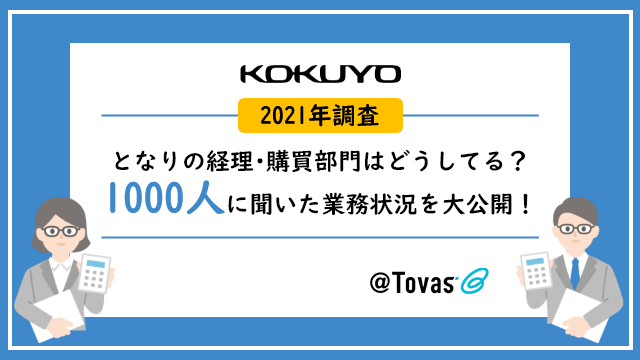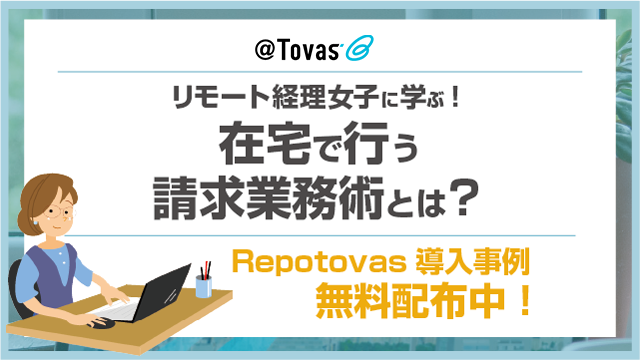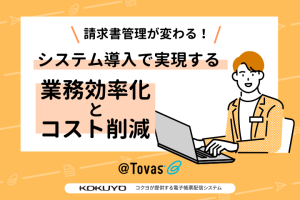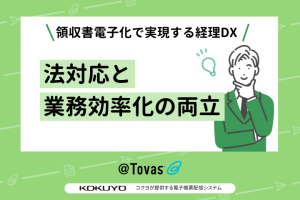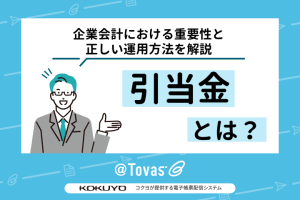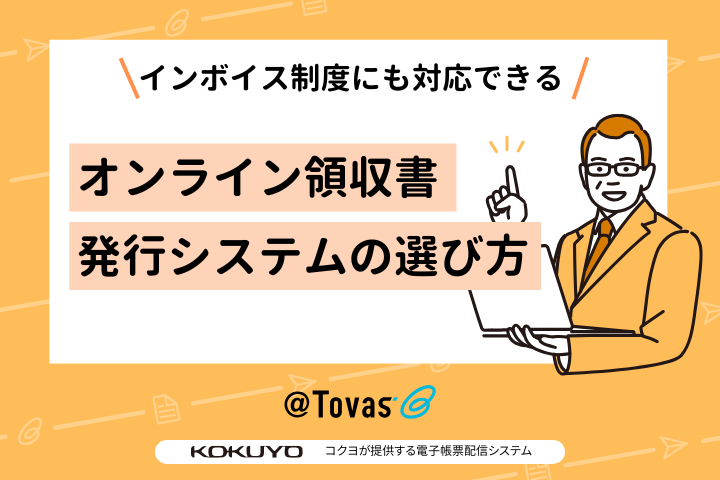
インボイス制度にも対応できるオンライン領収書発行システムの選び方
公開日:2024年12月23日 更新日:2025年3月23日
領収書の発行業務は、企業の経理部門にとって基幹的な業務の一つです。経費精算や会計処理に不可欠なこの作業も、従来型の紙ベースの運用では、発行から保管、検索に至るまで、大きな業務負荷がかかっています。しかも、2024年1月から電子取引データの保存義務が完全施行され、領収書のデジタル化は待ったなしの課題となっています。
本記事では、インターネットを活用した領収書発行の実務的なメリットと導入のポイントについて、詳しく解説します。
TOPICS
オンライン領収書発行が不可避となる背景

電子保存の完全義務化がスタート
電子取引データの電子保存義務は、本来2022年1月から完全施行される予定でした。しかし、事業者の対応状況を考慮し、2023年12月末まで宥恕措置が設けられ、やむを得ない事情がある場合は紙での保存が認められていました。
この宥恕措置は2023年末で終了し、2024年1月からは新たな猶予措置へと移行しています。ただし、この猶予措置は、システムやワークフローの整備が間に合わないなど、真にやむを得ない事情がある場合にのみ、税務署への申請・承認を経て認められるものです。単なる経営判断や資金繰りといった理由では認められず、電子保存に向けた具体的な取り組みが求められています。
紙の領収書管理から脱却する必要性
紙の領収書管理には、発行時の手作業による時間的コスト、保管スペースの確保、経年劣化による判読性の低下、必要な領収書の検索にかかる時間など、様々な非効率が存在します。
テレワークの普及により、オフィスに出社せずとも領収書の発行や確認が必要なケースが増加しており、紙の領収書では迅速な対応が困難になっています。新制度への対応を機に、これらの課題を解決する必要があります。
電子化なくして法令遵守なし
猶予措置を受けた場合でも、電子データのダウンロードと、その出力書面の提示・提出の両方に対応できる体制が必要です。結果として二度手間の保存作業を強いられることになり、業務効率の観点からも本質的な解決とはなりません。
インボイス制度への対応も同時に求められており、適格請求書等として扱われる領収書には、登録番号の記載や税率区分の明示が必須となっています。これらの要件に正確に対応するためには、システマティックな管理体制の構築が不可欠です。
このような状況において、インターネットを活用した領収書発行への移行は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。実際の対応においては、自社の状況を適切に評価し、計画的なシステム導入を進めることが求められます。
オンライン領収書発行による業務改善効果

コスト削減効果
領収書の電子化は、複数の側面でコスト削減をもたらします。最も分かりやすい効果として、電子領収書には収入印紙が不要となることが挙げられます。取引金額が大きい企業ほど、この印紙税削減の効果は大きくなります。
保管に関するコストも大きく削減できます。従来は領収書の保管のために専用のスペースや耐火金庫が必要でしたが、電子化によってこれらの物理的なスペースを他の用途に転換できます。文書保管箱の購入費用や、セキュリティ設備の維持費など、付随的なコストも削減対象となります。
経理業務の効率化
オンラインでの領収書発行は、経理担当者の業務時間を大幅に削減します。手書きでの発行作業や、発行後の整理・ファイリング作業が自動化されることで、業務効率が向上します。
特筆すべきは、データ管理の効率性です。電子帳簿として保存された領収書データは、取引先名や日付による検索が即座に可能となります。経費精算システムと連携することで、仕訳作業の自動化も実現できます。これにより、検索や集計にかかる時間を大幅に削減できます。
法令遵守体制の強化
電子帳簿保存法への対応において、オンライン領収書発行システムは重要な役割を果たします。電子取引データの保存義務化に対応するためには、適切なシステムの導入が不可欠となっています。
インボイス制度対応も重要な要素です。適格請求書等としての領収書には、登録番号や税率区分など、より詳細な記載が必要となります。これらの要件に対して、システムによる自動チェック機能を活用することで、記載漏れや誤記入のリスクを低減できます。登録番号の確認や税率区分の記載といった作業を自動化することで、業務効率の向上と同時に、正確性の担保も実現できます。
このように、オンライン領収書発行への移行は、単なる業務効率化だけでなく、法令遵守と業務品質の向上を同時に実現する効果的な手段となります。
領収書のオンライン発行手法の比較

インターネットを活用した領収書発行には、企業規模や業務形態に応じて複数の選択肢があります。それぞれのアプローチには特徴があり、導入目的や運用体制に応じて最適な方法を選択することが重要です。
クラウド会計ソフトの活用
中小企業や個人事業主向けの選択肢として、クラウド会計ソフトの活用が挙げられます。電子帳簿保存法の要件に準拠したデータ保存機能を備えており、経理作業の効率化を支援します。
会計処理との連携が可能である点も特徴的です。データの一元管理により、経理業務全体の効率化を図ることができます。
経費精算システムにおける発行機能
経費精算システムは、従業員の経費精算業務を電子化するためのシステムとして広く知られています。申請から承認までの一連の流れを電子化でき、領収書のデータ化から経費申請、承認、支払いまでが自動化されます。
特に従業員数の多い企業や、経費精算の処理件数が多い企業において、その効果を発揮します。承認プロセスのシステム化により、承認状況の可視化と処理の迅速化が実現できます。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したシステムを活用することで、法令遵守と業務効率化の両立も可能です。
基幹システムとの連携
既存の基幹システムと連携した領収書発行の方法も選択肢として挙げられます。基幹システムとの連携には大きく二つのアプローチがあり、従来型の方式では基幹システムに宛先マスタ情報を保持させる必要がありました。
しかし現在では、@Tovas Master+のようなクラウド型のサービスにより、基幹システムの改修なしでの導入が可能となっています。取引先の宛先情報をクラウド上で管理し、取引先自身が情報を更新できる仕組みにより、常に最新の情報を維持することができます。
これにより得られる効果は複数あります。まず、請求処理担当者の作業負荷が軽減されます。宛先情報の更新や確認作業が自動化され、郵送対応からの脱却も進めやすくなります。加えて、取引先との間で正確な宛先情報を共有できることで、配信ミスのリスクも低減できます。
システム面でも利点があります。クラウド上での一元管理により、情報の追加・更新・削除がスムーズに行えます。また、基幹システムの改修が不要なため、導入時の負担やコストを抑えることができます。必要に応じて段階的に機能を拡張していくことも可能です。
このように、基幹システムとの連携を検討する際は、従来型の連携方式に加えて、クラウドを活用した新しい連携方式も選択肢として考慮に入れる価値があります。システム改修の規模や運用後の管理負荷なども含めて、総合的に判断することが望ましいでしょう。
オンライン領収書発行システムの選定ポイント

オンライン領収書発行システムの選定では、法令対応やセキュリティといった基本要件を満たしていることは大前提となります。しかし、実際の導入効果を左右するのは、システムが日々の業務にどれだけフィットするかという点です。ここでは、成功につながる選定のポイントについて解説します。
業務視点での適合性
システム選定で最も重視すべきは、実務担当者の業務効率を高められるかどうかです。そのため、デモ環境やトライアル期間を利用して、実際の業務フローに沿った操作性を確認することが重要となります。
領収書の発行から保存までの一連の作業を実務担当者自身が試用し、実際の操作性を評価します。よく使う機能へのアクセスのしやすさや、必要な情報の入力のしやすさが、日々の業務効率を大きく左右するためです。画面遷移が多すぎたり、入力項目が散在していたりすると、作業効率の低下につながりかねません。
経費精算システムとの連携や会計処理との連動など、関連業務との親和性も重要な評価ポイントとなります。特に、月次処理や締め処理など、繁忙期の業務フローにおける使いやすさは入念に確認しておく必要があります。
法令対応と信頼性
電子帳簿保存法への対応は、システム選定における必須要件です。特に電子取引データの保存要件や、タイムスタンプ要件などへの対応状況を確認する必要があります。インボイス制度においても、適格請求書の要件を満たした領収書が発行できるかどうかを確実に確認しておきましょう。
セキュリティ面では、データの暗号化やアクセス制御の仕組みが実装されているかを確認します。また、システムの安定性という観点から、バックアップ体制や障害時の復旧手順についても事前に把握しておくことが重要です。
サポート体制の充実度
導入時のサポートから日常的な運用支援まで、充実したサポート体制があるかどうかも重要な判断材料となります。初期設定や既存データの移行に関する支援体制に加え、実際の運用開始後のフォローアップ体制についても確認が必要です。
日常的な運用においては、システムの不具合や操作方法について問い合わせできる窓口の充実度も重要です。特に、受付時間や対応手段(電話、メール、チャットなど)が自社の業務時間帯と合致しているかどうかを確認しておきましょう。
将来を見据えた拡張性
業務規模の拡大や新たな法制度への対応など、将来的な要件の変化にも柔軟に対応できる拡張性を持ったシステムを選択することが望ましいでしょう。
基幹システムとの連携可能性や、データ連携の方式についても、将来的な業務効率化を見据えて検討します。システムの機能を段階的に拡張できる柔軟性があれば、初期の導入負荷を抑えながら、徐々に活用範囲を広げていくことも可能です。
@Tovasによる電子帳票システムの特長

ここまで、オンライン領収書発行システムの必要性と選定のポイントについて解説してきました。ここでは、コクヨが提供する帳票Web配信クラウドサービス「@Tovas」の特長について説明します。
業務効率化を実現する配信機能
@Tovasは、経理・購買・営業部門で使用する請求書、納品書、注文書などの帳票を、電子ファイル、FAX、郵送など、取引先に応じた手段で配信できます。従来手作業で行っていた帳票の印刷、仕分け、配送作業を効率化し、大量送信にも対応。FAXサーバや専用回線を用意する必要もありません。
安全性を重視した配信環境
@Tovasは、重要な帳票を安全に配信するための機能を複数備えています。基本となる「ファイル送信機能」では、SSL暗号化通信を採用し、データの盗聴や改ざんを防ぎます。さらに、受信したファイルは自動的にウイルスチェックを行うため、安心してご利用いただけます。
受信側の操作も安全性を考慮して設計されています。受信者には専用のダウンロード用URLが記載された通知メールが届き、このURLからのみファイルを取得できます。送信者は専用の管理画面で、いつ誰がファイルを受け取ったかを確実に把握できます。
より厳格な管理が必要な場合には、「ファイル往復便」機能が利用できます。この機能では、送信ファイルごとに専用の返信用WEBサイトが自動で作られ、送受信の記録を確実に残すことができます。下請法の電子取引でも求められる「確実な送達」と「受領の証明」を、シンプルな操作で実現します。
取引先との定期的なやり取りには「私書箱機能」が便利です。郵便の私書箱のように、取引先ごとの専用の送受信スペースを用意。注文書や請求書など、重要な帳票を安全に保管・管理できます。基幹システムと直接連携することで、手作業による転記ミスや誤送信のリスクも防ぎます。
これらの機能により、取引金額や個人情報を含む帳票も、安全かつ確実に電子配信できます。情報セキュリティの国際規格(ISMS)を取得したコクヨが、システムの運用を一貫して管理しています。
基幹システムとのシームレスな連携
現在使用中のシステムとの柔軟な連携が可能です。特に@Tovas Master+では、取引先招待機能により、取引先自身が情報を入力できる仕組みを提供。従来は基幹システムで保管する必要があった宛先情報を、クラウド上で管理できるようになりました。これにより、基幹システムへの宛先情報の保管が不要となり、導入時の手間や費用を削減できます。
専門性に基づくサポート体制
コクヨは帳簿・伝票販売から100年以上の実績を持ち、2004年の@Tovasサービス開始以来、専任のサポート体制を築いてきました。初めて利用する方への説明から具体的な導入プラン提案まで、きめ細かなサポートを提供しています。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、請求書や納品書などの帳票書類を電子化して送付できるクラウドサービスです。発行した書類は電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存できるため、領収書をはじめとした書類の電子化に貢献できるでしょう。取引書類の発行・送付にかかる業務効率化を目指している場合は、ぜひご利用ください。