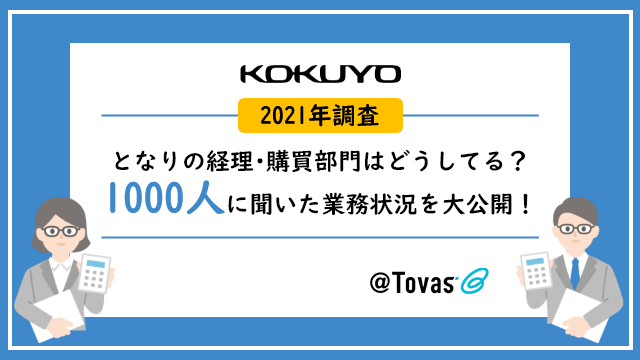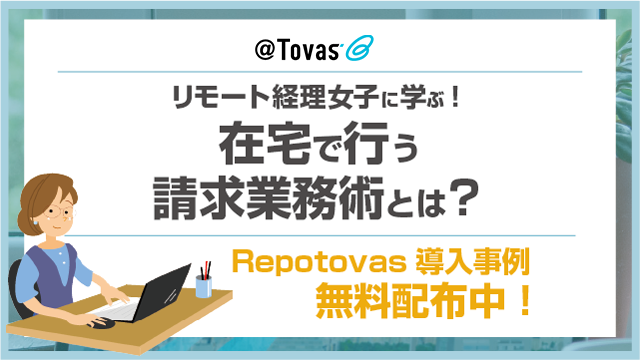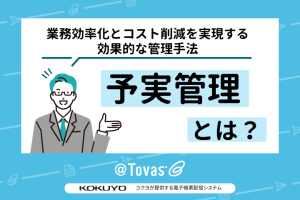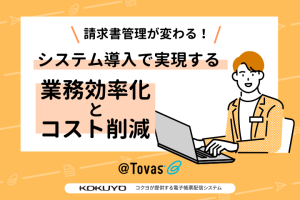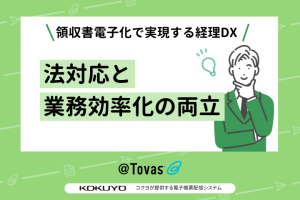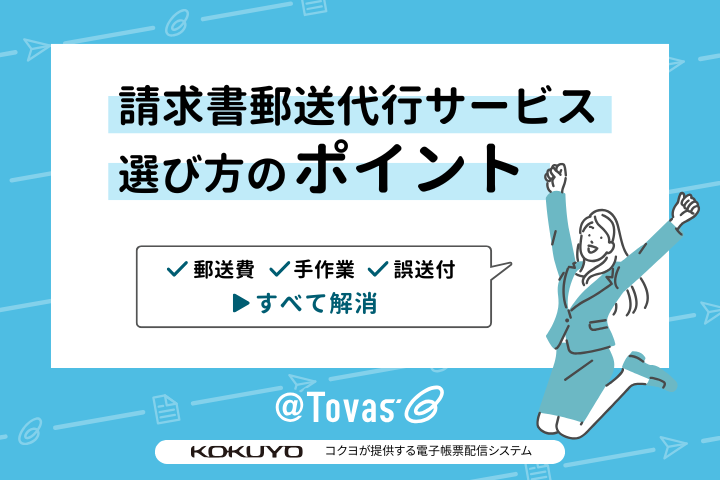
請求書郵送代行サービス 選び方のポイント
公開日:2024年12月18日 更新日:2025年3月23日
多くの企業にとって、請求書の郵送業務は欠かせない業務プロセスの一つです。しかし、従来の郵送方法では時間とコストがかかり、人的ミスのリスクも高くなりがちです。さらに2024年10月の郵便料金改定により、業務コストの見直しが急務となっています。
本記事では、請求書郵送業務の効率化とコスト削減を実現する手段として、郵送代行サービスに焦点を当て、その特徴や選び方について詳しく解説します。
TOPICS
請求書郵送業務の現状と課題

企業経営において請求書の確実な発送は、キャッシュフロー管理の要となる重要な業務です。しかし、多くの企業では従来型の郵送方法を継続しており、業務効率とコストの両面で大きな課題を抱えています。
企業における請求書郵送業務の実態
請求書の郵送業務では、印刷、封入、宛名記入、切手貼付、投函など、多くの手作業が必要となります。特に月末や期末などの繁忙期には、これらの作業に多くの時間と人手を要し、本来注力すべき経理業務に支障をきたすケースも少なくありません。
従来の郵送方法が抱える問題点
従来型の請求書郵送には、主に以下のような課題があります。
まず、人的リソースの観点から見ると、宛名記入や封入作業などの手作業に多くの時間を取られ、業務効率が著しく低下します。特に大量の請求書を扱う場合、この非効率さはより顕著となります。
次に、手作業による人的ミスのリスクも無視できません。宛先の記入ミスや封入ミス、さらには発送忘れなどが発生すると、キャッシュフローへの悪影響だけでなく、取引先との信頼関係にも傷がつく可能性があります。
2024年10月の郵便料金改定による影響
さらに、2024年10月1日からの郵便料金改定により、従来の郵送コストはさらに上昇することが予想されます。この料金改定は、定形郵便物や定形外郵便物など、企業の請求書発送に関わる主要な郵便サービスに影響を与えます。
料金改定に伴うコスト増加は、特に大量の請求書を定期的に発送する企業にとって、無視できない経営課題となっています。このような状況下で、多くの企業が請求書発送業務の効率化とコスト削減の両立を迫られています。
請求書郵送代行サービスとは
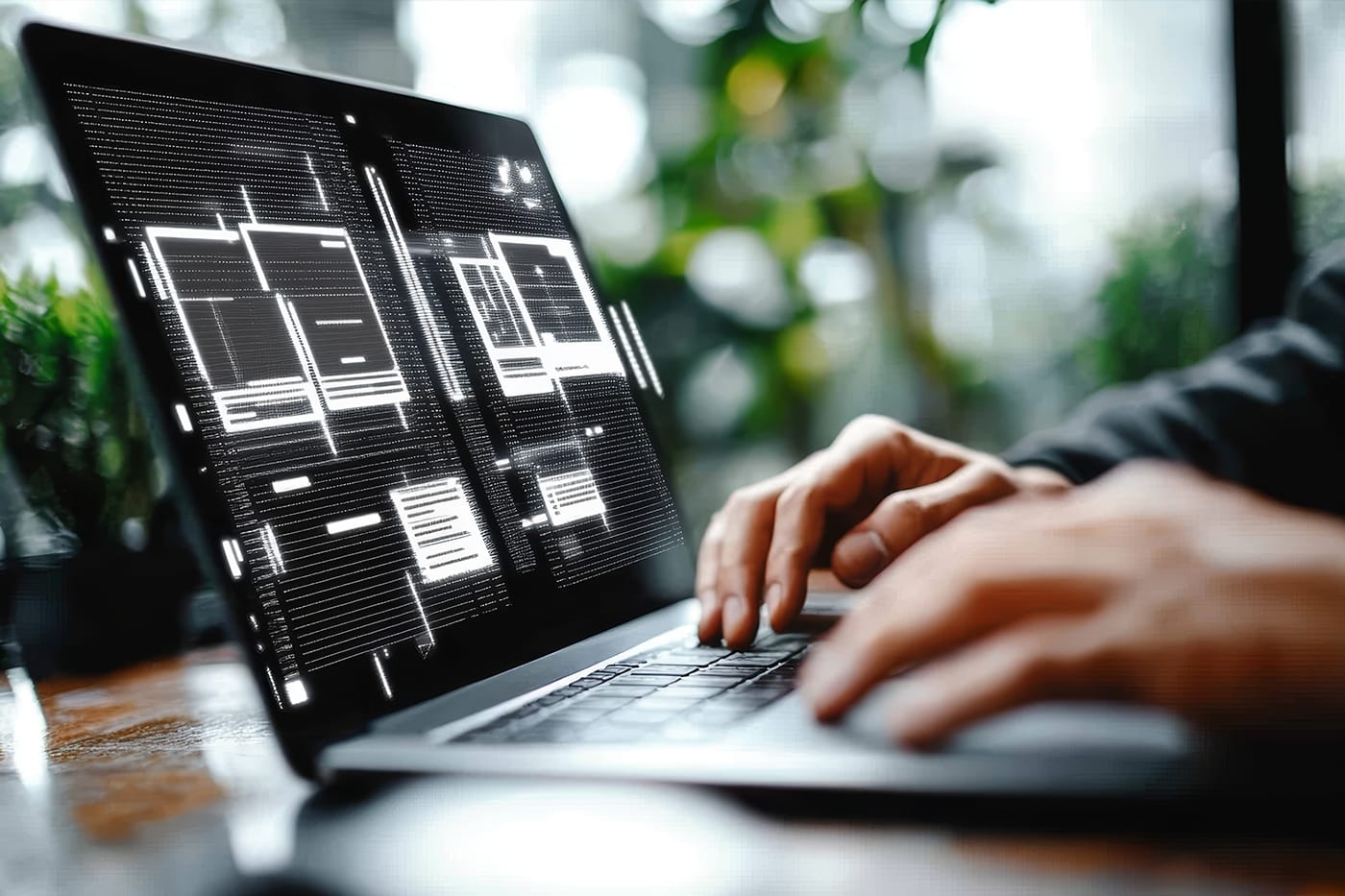
昨今、請求書の郵送業務を効率化する手段として注目を集めているのが、クラウドベースの郵送代行サービスです。ここでは、その基本的な仕組みから具体的なメリットまでを詳しく解説します。
郵送代行サービスの基本的な仕組み
郵送代行サービスは、請求書データをクラウド上で管理し、印刷から封入、発送までの一連の作業を自動化するシステムです。利用企業は、パソコンやタブレットからインターネット経由でシステムにアクセスし、請求書の作成から発送指示までを行うことができます。
特にクラウド型のサービスでは、請求書データの作成から送付状況の管理まで、すべての工程をオンラインで完結できることが特徴です。基幹システムとの連携により、請求データを自動で取り込み、発送までの工程を自動化することも可能です。
主なサービスの種類と特徴
請求書の郵送代行サービスは、主にクラウド型配信サービス、従来型の郵送代行サービス、ハイブリッド型サービスの3つに分類されます。
クラウド型配信サービスは、請求書データの作成からデータ保管、発送管理までを一元的に行えます。インターネット環境があればどこからでもアクセス可能で、基幹システムとの連携も容易という特徴があります。従来型の郵送代行は、PDFなどの電子データを郵送センターに送付し、印刷・封入・発送を委託する形式です。クラウド型に比べてシステム連携の柔軟性は劣りますが、既存の業務フローを大きく変更せずに導入できるメリットがあります。
ハイブリッド型サービスは、クラウド型と従来型の特徴を組み合わせ、企業の状況に応じて柔軟な運用が可能です。基幹システムとの連携機能を持ちながら、必要に応じて従来の郵送プロセスも活用できる特徴があります。
導入による具体的なメリット
郵送代行サービスの導入により、以下のような具体的なメリットが期待できます。
まず、コスト削減効果については、印刷用紙や封筒、インク代などの消耗品費の削減に加え、作業時間の短縮による人件費の抑制が実現できます。特に大量の請求書を定期的に発送する企業では、スケールメリットによる郵送料金の削減も期待できます。
業務効率化の面では、従来は手作業で行っていた印刷、封入、発送作業が自動化されることで、経理担当者の作業負担が大幅に軽減されます。これにより、より重要な経理業務に時間を振り向けることが可能になります。
また、人的ミス防止の観点からも、郵送代行サービスは大きな効果を発揮します。宛先情報のデータベース化により、入力ミスや送付先の取り違えを防止できるほか、発送状況をシステム上で一元管理することで、発送忘れなどのリスクも最小限に抑えられます。
さらに、多くのサービスでは発送履歴や配達状況をリアルタイムで確認できる機能を備えているため、取引先からの問い合わせにも迅速に対応することが可能です。請求書の到着確認や再発行依頼などにも、システム上で効率的に対応できます。
また、クラウドベースのサービスでは、請求書データがセキュアな環境で保管されるため、災害時のバックアップとしても機能します。紙の請求書を保管する物理的なスペースも不要となり、オフィススペースの有効活用にも貢献します。
業務改善を成功させる選び方

請求書郵送代行サービスの導入は、単なる郵送業務の外部委託ではなく、業務プロセス全体の改善機会として捉える必要があります。ここでは、導入効果を最大化するための重要なポイントについて解説します。
サービス選定の重要ポイント
郵送代行サービスを選定する際は、以下の観点から総合的に評価することが重要です。
まず、自社の発送業務の特性を正確に把握することから始めます。月間の請求書発行件数、発送のタイミング、請求書のフォーマット、特殊な要件(専用封筒の使用など)といった基本的な要件を整理します。これらの要件に対して、検討するサービスが十分に対応できるかを確認する必要があります。
また、業務効率化の観点からは、請求書データの作成から発送指示までの操作性も重要な判断基準となります。特に繁忙期には大量の請求書を処理する必要があるため、直感的な操作画面や一括処理機能の有無は、実務担当者の負担に大きく影響します。
基幹システム連携の重要性
業務改善の効果を最大限に引き出すためには、基幹システムとの連携が鍵となります。@Tovasでは、既存の基幹システムと柔軟に連携し、請求データの自動連携から発送までをシームレスに実行できます。
この連携により、請求データの手動入力や転記作業が不要となり、作業時間の短縮とミス防止の両面でメリットが得られます。また、請求書の発行から発送までの状況を一元管理できることで、業務の可視化も実現できます。
基幹システム連携を検討する際は、以下の3点に特に注意が必要です。
まず、既存システム環境との親和性について、システムの技術仕様や連携方式を具体的に確認します。API連携やCSVデータの取り込みなど、複数の連携方式に対応しているサービスを選ぶことで、将来的なシステム更新にも柔軟に対応できます。
次に、データの整合性確保の方法について確認が必要です。特に請求データの連携においては、金額や取引先情報の正確な転送が不可欠です。システムが提供する検証機能やエラー検知の仕組みについても詳しく確認しておきましょう。
さらに、連携テストの実施方法と期間についても事前に確認しておくことが重要です。本番環境への移行前に十分なテスト期間を確保できるか、テスト環境の提供有無なども重要な確認ポイントとなります。これにより、スムーズな導入と安定した運用を実現することができます。
セキュリティ対策の考え方
請求書には取引先の重要な情報が含まれるため、セキュリティ対策は特に慎重に検討する必要があります。
具体的なセキュリティ要件として、データの暗号化、アクセス権限の管理、操作ログの記録などが挙げられます。特に、クラウドサービスを利用する場合は、データセンターのセキュリティ認証取得状況や、定期的なセキュリティ監査の実施状況なども確認すべきポイントとなります。
また、万が一の事故や災害時に備えたバックアップ体制や、システムの可用性についても評価が必要です。特に、基幹業務である請求書発行を止めないためには、システムの安定性と障害時の対応体制が重要な判断基準となります。
請求書郵送代行サービス選びで失敗しないための3つの評価ポイント

請求書郵送代行サービスの選定においては、コスト、運用、システム連携の各観点から総合的な検討が必要です。ここでは、具体的な判断のポイントについて解説します。
コスト面での比較ポイント
サービス選定において重要となるコストは、初期費用と運用コストの2つに大きく分けられます。初期費用としては、システム利用料、導入支援費用、社内システムの設定・調整費用などが発生します。これらの費用は、サービスの規模や機能によって大きく異なるため、自社の予算規模に合わせて慎重に検討する必要があります。
運用コストについては、月額の基本料金に加えて、発送量に応じた従量課金が一般的です。従量課金の方式には、発送件数単位の課金、ページ数による課金、封筒の種類による料金設定などがあります。特に発送量が多い企業では、スケールメリットを活かせる料金体系を選択することで、大幅なコスト削減が可能となります。
運用面での比較ポイント
実務での使いやすさを評価する際は、請求書データの登録・管理の容易さ、一括処理機能の充実度、宛名データの管理機能、発送状況の確認のしやすさなどがポイントとなります。特に月末の繁忙期には大量の請求書を処理する必要があるため、直感的な操作画面と効率的な一括処理機能の有無は、実務担当者の負担に大きく影響します。
また、導入後の安定運用のために、サポート体制も重要な判断基準となります。@Tovasでは、電話・メールによる充実したサポート体制を整えており、トレーニング提供から日常的な問い合わせ対応、緊急時のサポートまで、一貫したサポートを提供しています。特に導入初期は、社内での運用方法の確立に様々な不安や疑問が生じやすいため、手厚いサポート体制の有無は重要な選定ポイントとなります。
システム連携と拡張性
システム連携の方式は、自社の環境に適したものを選択する必要があります。API連携による自動データ連携、CSVファイルによるデータ取り込み、基幹システムからの直接出力対応など、様々な連携方式が提供されています。@Tovasは、多様な基幹システムとの連携実績があり、シームレスな業務フローの構築が可能です。
将来的な事業拡大や制度変更にも対応できる拡張性も、重要な検討ポイントです。発送量の増加への対応、新しい請求形式への対応、電子帳簿保存法などの法令対応、他の業務システムとの連携可能性など、長期的な視点での評価が必要です。特にクラウドベースのサービスでは、システムのアップデートが随時行われるため、最新の要件にも柔軟に対応できます。
このように、サービス選定にあたっては、単純な機能比較だけでなく、コスト、運用、システム連携の各側面から総合的に評価することが重要です。企業の規模や業務特性によって最適な選択は異なりますが、長期的な活用を見据えた慎重な検討が必要です。
請求書郵送代行サービス導入のための準備と進め方

請求書郵送代行サービスの導入を成功させるためには、適切な準備と計画的な進め方が重要です。ここでは導入に向けた具体的なステップと、社内での合意形成のポイントについて解説します。
現状分析と課題の見える化
導入の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。まず請求書の発行量や郵送コスト、作業時間などの基本的なデータを収集します。これらの数値は、導入後の効果測定の基準となるだけでなく、経営層への提案時の根拠資料としても重要な役割を果たします。
現状分析では、単なる作業時間やコストだけでなく、繁忙期の人員配置や残業時間、ミスの発生状況なども含めて包括的に調査します。これにより、郵送代行サービス導入による具体的な改善効果を予測することができます。
社内での合意形成とスケジュール設定
導入プロジェクトを円滑に進めるためには、関係部署との早期からの調整が不可欠です。経理部門だけでなく、情報システム部門や経営企画部門など、関連する部署を特定し、それぞれの懸念事項や要望を事前に把握しておきます。
スケジュールの設計では、年度末や月末など、業務の繁閑を考慮した計画を立てることが重要です。特に基幹システムとの連携が必要な場合は、システム部門の作業時間や、テストに必要な期間も考慮に入れる必要があります。
@Tovasによる業務改善
@Tovasは電子帳票配信システムとして、企業の請求書郵送業務を効率化します。請求書データをシステムに登録するだけで、印刷から郵送までの作業を全て代行することができます。導入企業様の事例では、請求書・納品書のWEB配信への切り替えにより、作業時間を120時間削減し、送付コストを20分の1に抑えることに成功しています。
具体的な導入ステップ
@Tovasの導入は、以下のような段階的なアプローチで進めることをお勧めします。
まず、少数の取引先を対象にした試験運用からスタートし、課題や改善点を確認しながら段階的に拡大していきます。
導入初期は、社内の業務フローの見直しと並行して、新システムの操作研修も必要です。@Tovasは直感的な操作性を備えていますが、効率的な運用のためには、担当者への適切なトレーニングが重要となります。
トラブルを防ぐため、移行期間中は従来の郵送方式と並行して運用することをお勧めします。この二重運用期間中に、システムの動作確認や業務フローの最適化を行い、安定運用の目処が立った段階で完全移行を行います。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、導入の容易さと即効性のある効果により、企業の規模や業種を問わず、幅広い企業で活用可能です。「電子ファイル」「FAX」「郵送」の3つの配信手段を選べるため、取引先に応じた対応が可能です。郵送費の削減を目指している場合は、ぜひご利用ください。