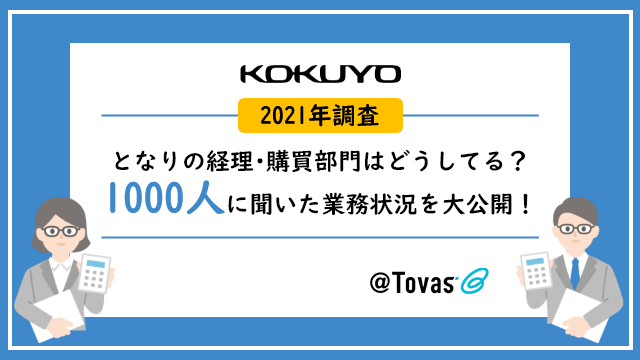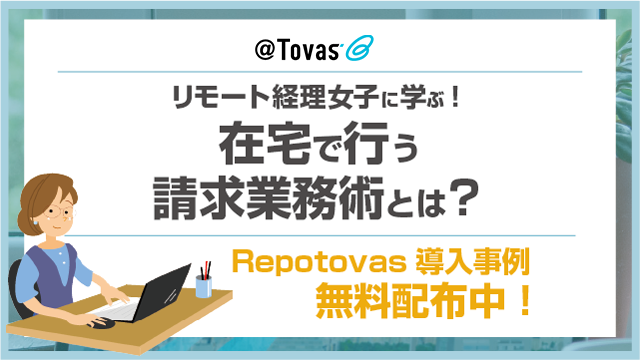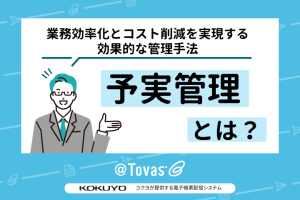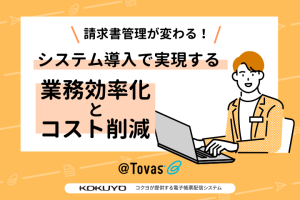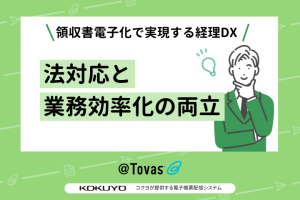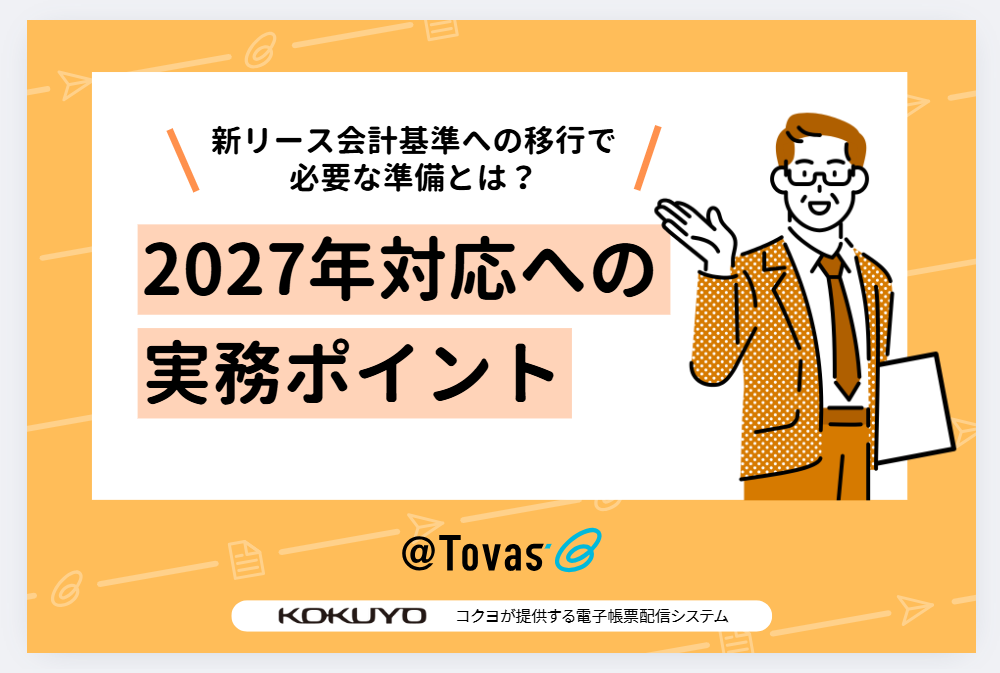
新リース会計基準への移行で必要な準備とは?2027年対応への実務ポイント
公開日:2024年12月17日 更新日:2025年3月23日
企業経営において、リース取引は設備投資や事業展開の重要な手段として活用されています。しかし、この度の新リース会計基準の公表により、多くの企業で会計実務の見直しが必要となっています。
本記事では、新リース会計基準への対応に向けて、実務担当者が押さえるべきポイントを詳しく解説します。
TOPICS
新リース会計基準の変更で企業に求められる対応
 2024年9月、企業会計基準委員会(ASBJ)は新しいリース会計基準を公表しました。この新基準は、企業の財務報告に大きな変革をもたらします。特に注目すべきは、借手側の会計処理が大きく変わることです。
2024年9月、企業会計基準委員会(ASBJ)は新しいリース会計基準を公表しました。この新基準は、企業の財務報告に大きな変革をもたらします。特に注目すべきは、借手側の会計処理が大きく変わることです。
新基準の概要と適用時期について
新基準の特徴は、これまでの会計処理を根本から見直す点にあります。従来の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類していました。
しかし、新基準ではこの区分がなくなり、すべてのリースを貸借対照表に計上することになります。この変更により、企業の財務諸表はより実態に即した内容となります。
新リース会計基準の適用開始は2027年4月1日以降に始まる事業年度からとなります。企業は2027年の適用に向けて、十分な準備期間を確保することができます。早期適用も認められているため、自社の状況に応じた導入時期の検討が重要となります。
企業活動への影響について
新基準の導入は、単なる会計処理の変更にとどまりません。まず、財務諸表上では資産と負債の両方が増加します。これにより、自己資本比率などの財務指標に影響が出ることが予想されます。
次に、業務面では新たなシステム対応が必要となります。リース取引の管理方法を見直し、データの収集や計算の仕組みを整える必要があります。
さらに、契約管理の方法も変更が必要です。リース期間の判断や更新オプションの評価など、新たな実務判断が求められるためです。
早期対応の重要性について
新基準適用までの約2年半という期間は、実務対応の観点からは決して長くありません。そのため、計画的な準備が重要となります。
まずは現状把握から始める必要があります。自社が保有するリース契約を総点検し、新基準による影響を評価します。その結果に基づき、対応方針を決定していきます。
システム面での準備も重要です。新基準に対応したシステムの選定や導入には、十分な時間が必要となります。また、関係部門への説明や教育も並行して進める必要があります。
新リース会計基準における主要な変更点
 新リース会計基準は、企業の財務報告に大きな変革をもたらします。この変更は特に、借手としてリースを利用する企業の会計実務に重要な影響を与えます。以下では、新基準における重要な変更点とその影響について、実務的な観点から解説します。
新リース会計基準は、企業の財務報告に大きな変革をもたらします。この変更は特に、借手としてリースを利用する企業の会計実務に重要な影響を与えます。以下では、新基準における重要な変更点とその影響について、実務的な観点から解説します。
借手の会計処理の変更内容
新基準で最も注目すべき変更点は、借手の会計処理方法です。現行の基準では、リース取引を性質に応じて区分していました。新基準では、この区分がなくなり、統一された処理方法が導入されます。
たとえば、これまでオフバランスとされていた事務所の賃貸借契約も、新基準では資産計上が必要となります。同様に、営業用の車両リースなども、すべて貸借対照表に計上することになります。
この変更により、企業の財務諸表はより実態に即した内容となります。特に、多くの賃貸物件や営業用資産を保有する企業では、財務諸表の数値が大きく変動する可能性があります。
使用権資産とリース負債の計上方法
新基準では、リース取引開始時に「使用権資産」と「リース負債」という二つの項目を計上します。使用権資産とは、リース物件を使用する権利を表す資産のことです。
使用権資産の金額は、リース料の支払総額を現在価値に割り引いた金額が基本となります。これに加えて、契約開始時の費用や原状回復費用なども含めて計算します。
一方、リース負債は将来支払うリース料の合計額を現在価値に割り引いた金額です。この計算には、リース期間や割引率の設定が重要な要素となります。
オンバランス化が財務諸表に与える影響
新基準の適用により、企業の財務諸表には様々な変化が生じます。まず、貸借対照表では資産と負債の両方が増加します。これにより、自己資本比率が低下する可能性があります。
損益計算書では、費用の認識方法が変わります。現行基準では賃借料として計上していた費用が、使用権資産の減価償却費とリース負債の支払利息に分かれます。
キャッシュ・フロー計算書でも変更が生じます。リース料の支払いは、従来の営業活動から財務活動による支出として表示されることになります。
現行基準と新基準の主な違い
新基準と現行基準の違いは、会計処理の基本的な考え方にあります。現行基準では、リースの性質に応じて異なる会計処理を行っていました。
新基準では、すべてのリースを原則として資産計上します。これにより、企業間の比較可能性が高まることが期待されます。一方で、システム対応や業務プロセスの見直しが必要となります。
開示についても要件が変更されます。新基準では、使用権資産やリース負債に関する詳細な情報開示が求められます。これは投資家にとって、より詳しい情報提供につながります。
新基準対応に向けた準備のポイント
 前章で解説した新リース会計基準の変更点への対応には、包括的な準備が必要です。ここでは、円滑な移行のために必要となる具体的な準備について解説します。
前章で解説した新リース会計基準の変更点への対応には、包括的な準備が必要です。ここでは、円滑な移行のために必要となる具体的な準備について解説します。
リース契約の現状把握と影響度分析
新基準への対応において、最初に行うべきは自社のリース取引の総点検です。まずは、現在締結している契約を網羅的に確認することから始めます。
契約の確認では、事務所の賃貸借契約やOA機器のリース契約など、すべての契約を対象とします。契約書からは、リース期間や更新オプションの有無、支払条件などの重要な情報を抽出します。
次に、それぞれの契約について新基準適用時の影響を試算します。使用権資産とリース負債の概算額を算出し、財務諸表への影響を予測します。この分析結果は、経営層への説明資料としても活用できます。
基幹システムの対応検討
新リース会計基準への対応は、既存のシステムでは困難な場合が多く、業務効率化や正確性の向上といったメリットを実現するためには、新システムの導入が不可欠です。新システムの導入によって、人件費削減や誤入力防止によるコスト削減効果が期待できるだけでなく、法規制違反のリスクも軽減できます。
システム選定では、基幹システムや既存の会計システムとのデータ連携の自動化が重要なポイントとなります。たとえば、@Tovasのようなクラウド型システムでは、APIを通じた自動連携が可能です。これにより、データ入力の手間を大幅に削減できます。
また、契約情報の一元管理や減価償却計算、利息計算などの機能も重要です。開示資料の自動作成機能があれば、決算業務の効率化にもつながります。
業務プロセスの見直し
新基準への移行では、既存の業務プロセスも見直しが必要です。まず、契約管理の方法を整備します。新規契約の審査から契約終了時の処理まで、一連の流れを再設計します。
会計処理についても、新たな仕訳パターンの設定が必要です。月次決算や年度決算での処理手順を見直し、効率的な業務フローを構築します。
さらに、契約の承認プロセスも重要です。リース取引に関する決裁基準を見直し、適切な承認フローを整備することで、内部統制も強化できます。
社内教育・研修の実施方法
新基準への移行を確実なものとするために、計画的な教育・研修が重要です。経理部門向けには、新基準の詳細な理解とシステムの操作方法について、十分な研修を実施します。
他部門向けには、新基準の概要理解と契約時の留意点について説明します。特に、営業部門や総務部門など、リース契約に関わる部門への周知は重要です。
また、経営層への説明も欠かせません。財務諸表への影響や必要な投資について、具体的な数値を示しながら説明することで、スムーズな意思決定を促します。
新リース会計基準対応におけるシステム選択の重要ポイント
 新リース会計基準への対応では、適切なシステムの選択が成功の鍵を握ります。以下では、システム選択時の重要なポイントと、選択時の判断基準について詳しく解説します。
新リース会計基準への対応では、適切なシステムの選択が成功の鍵を握ります。以下では、システム選択時の重要なポイントと、選択時の判断基準について詳しく解説します。
基幹システムとの連携に関する要件
新基準対応システムの選択では、既存の基幹システムとの連携性が最も重要です。データ連携の方式として、APIによる自動連携が最も効率的です。APIとは、システム間でデータをやり取りするための仕組みのことです。
たとえば、@Tovasでは多様な基幹システムとの連携実績があります。これにより、契約データや会計データを自動的に連携させることができます。手作業でのデータ移行が不要となり、作業効率が大幅に向上します。
さらに、データの整合性を確保する機能も重要です。システム間でデータの不一致が発生した場合、自動的に検知して修正できる仕組みが必要です。
データ移行と管理の重要性
システム導入時には、既存のリース契約データの移行が必要となります。この際、データの正確性を確保することが極めて重要です。古いデータの修正や、不要なデータの整理なども必要となります。
日常的なデータ管理においては、契約情報の更新や変更を効率的に行える機能が必要です。特に、変動リース料の管理や契約内容の変更に柔軟に対応できることが重要です。
また、将来の経営判断に活用できるよう、データの分析機能も重要な要素となります。管理会計への活用や、経営分析に必要なデータを抽出できる機能があると便利です。
セキュリティ対策の確保
リース契約情報は重要な経営情報を含むため、高度なセキュリティ対策が必要です。まず、ユーザーごとに適切な権限を設定し、情報へのアクセスを管理します。
データの保護も重要な要素です。暗号化技術を用いたデータの保護や、定期的なバックアップ、災害時の復旧対策なども必要となります。
また、システムの操作履歴を記録し、不正アクセスを防止する機能も重要です。これらの機能により、安全なデータ管理が実現できます。
導入時の実務的な注意点
システム導入を成功させるためには、計画的な準備が必要です。まず、導入スケジュールを明確にし、必要な人員と予算を確保します。
次に、テスト環境を整備し、実際のデータを使用した検証を行います。この過程で発見された問題点は、本番環境への移行前に解決しておく必要があります。
また、システムの操作手順を文書化し、運用マニュアルを整備することも重要です。これにより、担当者の異動があっても安定した運用が可能となります。
運用体制の整備方法
システムの安定運用には、適切な体制整備が不可欠です。まず、システムの運用担当者を決め、その役割と責任を明確にします。
また、システムベンダーのサポート体制も重要な要素です。問い合わせ窓口の対応時間や、メンテナンス体制などを事前に確認しておく必要があります。
さらに、システムの運用状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて改善を行う体制も重要です。これにより、長期的な運用の安定性が確保できます。
今すぐ始めるべき対応と準備スケジュール
 新リース会計基準の適用開始まで残り約1年半という状況の中、準備の遅れは大きなリスクとなります。限られた時間の中で確実な対応を実現するため、計画的な準備が不可欠です。
新リース会計基準の適用開始まで残り約1年半という状況の中、準備の遅れは大きなリスクとなります。限られた時間の中で確実な対応を実現するため、計画的な準備が不可欠です。
段階的な準備の進め方
新基準への対応は、計画的に段階を追って進めることが重要です。まず、2026年3月までの準備フェーズでは、プロジェクトチームを立ち上げることから始めます。
この段階では、施行が1年延期されたことにより、十分な検討を行うことが可能となりました。この期間に社内の現状把握を行い、全リース契約を詳細に分析し、影響度調査を実施し、その結果に基づいて基本方針を策定します。影響度調査の結果に基づき、システム要件の洗い出しだけでなく、必要な予算の確保も並行して進めます。
次の体制整備フェーズは、2026年9月までを目安とします。この期間では、具体的なシステム要件の確定と運用体制の設計を進めます。業務フローの見直しや、社内教育の計画も立案します。
最後の導入フェーズは、2027年1月までに完了させることを目標とします。システムの導入と並行して、新しい業務フローを確立します。また、運用マニュアルの整備やテスト運用も実施します。
優先的に取り組むべき課題
限られた時間の中で、特に優先度の高い対応から着手することが重要です。現時点で最も急ぐべきは、リース契約の棚卸作業です。契約内容を精査し、新基準による財務影響を試算します。
また、システム構築の方針決定も急務です。既存システムとの連携方法や、新たに必要となる機能の検討を進めます。この際、基幹システムとの親和性が高い@Tovasのようなクラウド型システムの活用も有効な選択肢となります。
さらに、プロジェクト体制の確立も重要です。経理部門を中心に、関連部門を巻き込んだ体制を構築します。経営層への報告ラインも確立し、迅速な意思決定を可能にします。
新基準対応の成否は、適切なソリューションの選択にかかっています。特に、基幹システムとの連携が容易な@Tovasのようなクラウド型システムは、スムーズな移行を実現する有効な選択肢です。
コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』は、請求書や納品書などの帳票書類を電子化して送付できるクラウドサービスです。郵送やFAXによる送付にも対応可能で、取引先によって送付方法を選べます。
電子帳簿保存法に対応した形式で送った帳票を保管できるため、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度にも対応可能です。今後の新リース会計基準への移行に併せて会計システムの導入をご検討の場合はぜひご相談ください。