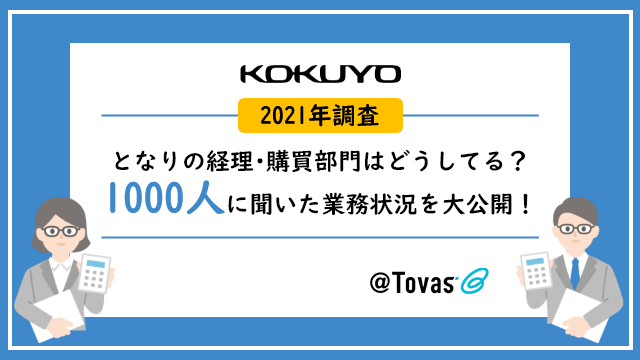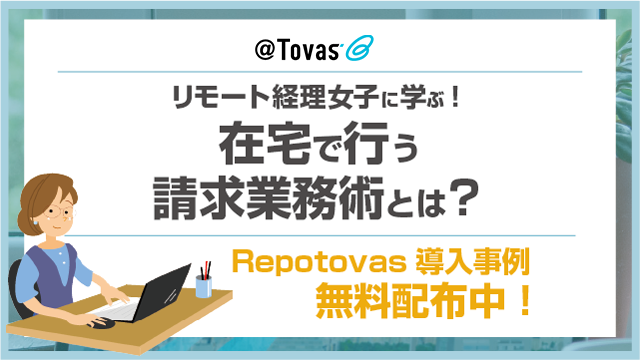関連会社とは?関係会社との違いや決算上の取扱い
公開日:2023年4月24日 更新日:2023年10月16日
連結決算の業務をする場合、複数の会社を一つの組織体として考えるため、関連会社や子会社など会社同士の関係性を理解することが重要です。それぞれの定義や、決算上の取扱いがよく分からないという方も多いかもしれません。
この記事では、関連会社とは何か、関係会社との違いや決算上の取扱いを解説します。関連会社設立のメリット・デメリットや、実務で役立つ仕訳方法もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
TOPICS
関連会社とは
関連会社とは、親会社が20%以上の議決権を保有しており、財務や事業方針の決定に強い影響力を持っている会社のことです。なお議決権が20%未満であっても、一定の要件に該当する場合は関連会社とされます。
関連会社は、子会社とはまた別の組織形態です。子会社は、議決権の50%以上を親会社が持っており、実質的に支配されています。関連会社は、子会社のように明確な主従関係があるわけではありませんが、親会社が強い影響力を持っています。
ただし関連会社だからといって、必ず連結決算の対象になるわけではありません。連結グループ全体への影響度に応じて、連結決算の対象に含めるかどうかが決められます。
関連会社に該当するかどうかの判定基準は?
前述のとおり、原則として20%以上の議決権を保有していれば関連会社とされますが、議決権以外の要件に当てはまるかどうかも判定基準となります。関連会社の判定基準は、以下の表のとおりです。
| 議決権保有比率 | 議決権以外の要件 |
| 20%以上 | なし |
| 15%以上20%未満 |
・親会社の社員等が役員等に就任している ・親会社が重要な融資をしている ・親会社が重要な技術を提供している ・親会社との間にビジネス上の重要な取引(仕入・販売など)が認められる ・財務や事業の方針決定で重要な影響があると考えられる事実が存在する 上記いずれかの要件に当てはまる場合 |
| 15%未満 | 特定の者の議決権とあわせて、自己所有等議決権数が20%以上、かつ上記のいずれかの要件に当てはまる場合 |
関連会社と子会社の違い
関連会社と子会社の大きな違いは、親会社によって支配されているかどうかですが、他にもさまざまな違いがあります。ここでは、関連会社と子会社の違いを詳しく解説します。
子会社とは
子会社とは、意思決定機関である株主総会で、親会社に支配されている会社のことです。原則として、親会社が50%を超える議決権を保有していれば、子会社としてみなされます。
親会社が50%を超える議決権を有しているということは、株主総会で子会社の意思決定の権利を親会社が握っていることです。関連会社のケースとは異なり、そこには完全な主従関係が認められます。
ただし株式の保有率が50%未満でも子会社になるケースもあります。例えば親会社から子会社へ役員が出向し、親会社が実質的に経営方針を決める場合は、保有率がどうであれ、親会社の意向に従わざるを得ません。
子会社の判定基準
前述のとおり、親会社の支配を受けている会社のことを子会社と呼びます。議決権が50%を超える場合だけでなく、一定の要件を満たすと子会社となります。子会社の判定基準は、以下の表のとおりです。
| 議決権保有比率 | 議決権以外の要件 |
| 50%超え | なし |
| 40%以上50%以下 |
親会社と同じ意思を持って議決権を行使する人の議決権とあわせて50%を超える。または次のいずれかの要件に当てはまる場合 ・取締役などに準ずる役職に自社の役員等が就任している ・他の会社に対して重要な融資・技術の提供・ビジネス上の取引(仕入・販売など)をしている |
| 40%未満 | 親会社と同じ意思を持って議決権を行使する人の議決権とあわせて50%を超える、なおかつ、上記のいずれかの要件に当てはまる場合 |
関連会社との違い
関連会社と子会社は、親会社の株式保有比率によって分けられます。株式保有比率が原則として20%以上であれば関連会社、50%を超える株式を保有している場合は子会社とされるのが一般的です。
さらに関連会社と子会社では、連結決算での会計処理の方法も異なります。具体的には、関連会社は「持分法」、子会社は「連結法」に基づいて会計処理を行います。
持分法は、関連会社や、連結対象ではない子会社に適用される方法です。個別の財務諸表を全て親会社に合算するのではなく、親会社に関連する部分だけを連結します。一方の連結法は、親会社と子会社の財務諸表を完全に連結させるものです。持分法とは異なり、子会社の財務状態がそのまま親会社に反映されます。詳しい内容は、後の項目で取り扱います。
関係会社と関連会社の違いとは?
関係会社とは、事業活動で密接な関係を持った会社の総称です。親会社や子会社、関連会社など、会計上の規定に該当するものは全て関係会社となります。関係会社というマクロな概念があり、そこに関連会社や子会社などが含まれているといったイメージです。
関連会社や子会社は、親会社との連結決算で、貸借対照表上の「関係会社株式」の勘定科目で計上されます。関連会社と子会社は出資比率や要件の違いで、「関連会社株式」もしくは「子会社株式」に分類されることになり、会計処理も別々です。
ちなみに関係会社というと、親会社を含まないというイメージもありますが、親会社もこちらの概念に含まれます(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条8項)。
関係会社や子会社の呼称・種類

関係会社の中には、関連会社や子会社の他にもさまざまな呼称や種類があります。混同しないように、それぞれの意味を理解しておくことが大切です。ここではグループ会社や持株会社など、関連会社や子会社の呼称・種類を解説します。
グループ会社
グループ会社とは、親会社や子会社、関連会社などの関係がある会社の全てを指します。ただしグループ会社には法的な規定があるわけでなく、あくまでもビジネス上で使われる用語です。一般的には法的に定められている関係会社と同じ意味で使われます。
ビジネス上、同じ親会社を持つ子会社は一般的に兄弟会社と呼ばれます。ただしこれらの用語は、ビジネスやメディアにおける表現として用いられるものであり、取引や契約などの場面での使用には注意が必要です。
持株会社
持株会社とは、他の会社を傘下に入れることを目的として、子会社の株式を保有する会社です。主に、純粋持株会社と事業持株会社の2種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
| 純粋持株子会社 | 事業は行わずに株式保有による支配をする |
| 事業持株会社 | 事業も行っている |
持株会社は、金融や小売などの幅広い業種で経営効率化を目的に設立されています。1997年に解禁されたばかりの比較的歴史の浅い概念です。
完全子会社
完全子会社とは、親会社が株式を100%保有している会社のことです。子会社の株式を100%持っている親会社は、完全親会社と呼ばれます。
完全子会社として認められるためには、親会社が株式を100%持っている必要があります。つまり相互会社の場合や、個人によって株式が保有されているような場合は、完全子会社に該当しません。
親会社の意向を完全に反映させられるため責任が明確であり、スピード感のある意思決定が可能です。
特定子会社
特定子会社とは、「企業内容等の開示に関する内閣府令」で定められた定義に該当する会社で、主に会計の場面で用いられる用語です。具体的には、以下のような条件があります。
・親会社の売上高または仕入高の総額が10%以上の子会社
・親会社の純資産額の30%以上を持つ子会社、もしくは、資本金または出資額が親会社の資本金の10%以上に相当する子会社
特定子会社は、子会社の中でも特に業績面で影響力が強いものとされています。
連結子会社
連結子会社とは、前述のように、親会社の連結財務諸表に連結される対象となる子会社のことです。連結決算で、財務状態がそのまま親会社の連結財務諸表に合算されます。
ただし子会社の中でも影響力や重要性が低い、もしくは親会社の支配が一時的なものにとどまるような場合は、連結の対象外になります。このような子会社を、非連結子会社と呼びます。
連結して決算を行うため、不正会計を防止できるのが大きなメリットです。
特例子会社
特例子会社とは、障がい者の雇用を促すために設立される子会社です。以下の条件を満たした場合に、特例子会社と認められます。
・親会社が子会社として支配していること(議決権の過半数を有しているなど)
・雇用される障がい者が5人以上、かつ全従業員に占める割合が20%以上であること
・雇用される障がい者の中でも、重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合が30%以上であること
・障がい者の雇用管理を適正に行えること
・雇用の促進や安定が確実に達成させると認められること
関連会社設立のメリット
関連会社設立のメリットは主に、意思決定の効率化、後継者の育成、節税効果の3つになります。ここではそれぞれのメリットを詳しく解説します。
意思決定の効率化
意思決定の効率化は、関連会社を設立する代表的なメリットです。組織が大きくなるほど、株主総会や取締役会で承認を得るのが難しくなります。意思決定のスピードダウンが起きれば、企業の競争力にも影響が出てくるでしょう。
そこで関連会社(子会社)を設立し、少人数の取締役が経営を担うことで、スピーディーな意思決定が可能になります。さらに別会社にして事業を切り分ければ事業売却も容易です。
後継者の育成
後継者の育成も大きなメリットです。関連会社の経営を後継者に任せることで、後継者の育成につながります。
後継者候補が複数存在する場合に、それぞれ別の会社を継がせることもできます。例えば後継者候補として複数人の親族がおり、それぞれ会社を継がせたいといったケースもあるでしょう。
上記の場合、関連会社を複数設立していれば、「親会社を子どもに継がせる」「関連会社を他の親族に継がせる」といった方法も可能です。
節税効果
関連会社を設立することで親会社の利益が分散され、節税効果につながるといったメリットも見逃せません。資本金額によっては、法人税や地方法人税、消耗品の軽減措置を受けられる可能性もあります。
事業の切り分けは節税効果だけではありません。リスク管理として関連会社を設立するケースもあります。例えば多くの投資が必要な部門を作る際に、親会社にそのまま設置するのではなく関連会社として設立すれば財務リスクを軽減できます。
関連会社設立のデメリット
関連会社設立にもいくつかのデメリットがあります。関連会社などが不祥事を起こすと、親会社を含めたグループ会社全体に影響を及ぼす可能性があることです。親会社が直接不祥事に関わっていなくても、結果として、経営に大きな影響を与えるリスクがあります。
さらに親会社の影響力が強すぎると、関連会社の経営能力が失われてしまい、親会社に依存してしまう可能性もあります。関連会社設立を検討している場合は、メリット・デメリットをよく整理しておくことが重要です。
関連会社の決算上の取扱い
関連会社や子会社がある場合は、親会社と一つの組織体としてみなし、連結決算を行う必要があります。ここでは主な会計処理や持ち分法適用会社、持ち分法と全部連結の違いを詳しく解説します。
関連会社や子会社の会計処理
関連会社や子会社がある場合は、連結決算で連結財務諸表を作成し、グループ会社全体の経営成績や財務状態を明確にしなければなりません。従来は、親会社のみの決算書(単独決算)で、グループ全体の経営成績・財務状況や、キャッシュフローを見ていました。
しかしこれでは関連会社や子会社を使った不正などもあり、会計の透明性が失われてしまいます。そこで連結財務諸表の作成が義務付けられるようになり、単独決算主義から連結決算重視の方向性に変わりました。
連結財務諸表では親会社と子会社間の取引は内部取引とされるため、より適切な経営状況の把握が可能になります。
持分法適用会社とは
持分法適用会社とは、連結財務諸表の作成に関して持分法の適用対象となる会社です。原則として、議決権所有比率20%以上かつ50%以下である会社を指します。
子会社の決算書を連結財務諸表に合算する際は、親会社との関係性に応じて各社を「連結子会社」「非連結子会社」「関連会社」に分ける必要があります。そして、それぞれに適用される決算方法によって親会社に連結させることが原則です。連結子会社は全部連結、非連結子会社と関連会社は、持分法がそれぞれ適用されます。
全部連結と持分法では、連結財務諸表の作成にあたって連結の処理が異なってきます。詳しい違いは次の項目で詳しく解説します。
持分法と全部連結の違い
持分法とは、親会社が関連会社などの持分法適用会社の資本と損益の中で、親会社に帰属する部分を連結決算に組み入れる方法です。全部連結とは異なり、財務諸表を全て合算する必要はなく、親会社に関連する部分のみ連結させます。
持分法のメリットは、全部連結に比べて会計処理がしやすい点です。全部連結の場合は、親会社と子会社の財務諸表を連結した上で、少数株主の持分を控除するなどの処理が必要になります。しかし持分法は、「投資有価証券」「持分法による投資損益」の2つの勘定科目を使って、親会社の財務諸表に反映させます。
なお持分法が適用される会社には、関連会社の他、親会社の支配が一時的または重要性の低い子会社(非連結子会社)もあります。
関連会社の会計処理

持株会社は、金融や小売などの幅広い業種で経営効率化を目的に設立されています。1997年に解禁されたばかりの比較的歴史の浅い概念です。
完全子会社
完全子会社とは、親会社が株式を100%保有している会社のことです。子会社の株式を100%持っている親会社は、完全親会社と呼ばれます。
完全子会社として認められるためには、親会社が株式を100%持っている必要があります。つまり相互会社の場合や、個人によって株式が保有されているような場合は、完全子会社に該当しません。
親会社の意向を完全に反映させられるため責任が明確であり、スピード感のある意思決定が可能です。
特定子会社
特定子会社とは、「企業内容等の開示に関する内閣府令」で定められた定義に該当する会社で、主に会計の場面で用いられる用語です。具体的には、以下のような条件があります。
・親会社の売上高または仕入高の総額が10%以上の子会社
・親会社の純資産額の30%以上を持つ子会社、もしくは、資本金または出資額が親会社の資本金の10%以上に相当する子会社
特定子会社は、子会社の中でも特に業績面で影響力が強いものとされています。
連結子会社
連結子会社とは、前述のように、親会社の連結財務諸表に連結される対象となる子会社のことです。連結決算で、財務状態がそのまま親会社の連結財務諸表に合算されます。
ただし子会社の中でも影響力や重要性が低い、もしくは親会社の支配が一時的なものにとどまるような場合は、連結の対象外になります。このような子会社を、非連結子会社と呼びます。
連結して決算を行うため、不正会計を防止できるのが大きなメリットです。
特例子会社
特例子会社とは、障がい者の雇用を促すために設立される子会社です。以下の条件を満たした場合に、特例子会社と認められます。
・親会社が子会社として支配していること(議決権の過半数を有しているなど)
・雇用される障がい者が5人以上、かつ全従業員に占める割合が20%以上であること
・雇用される障がい者の中でも、重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合が30%以上であること
・障がい者の雇用管理を適正に行えること
・雇用の促進や安定が確実に達成させると認められること
関連会社設立のメリット
関連会社設立のメリットは主に、意思決定の効率化、後継者の育成、節税効果の3つになります。ここではそれぞれのメリットを詳しく解説します。
意思決定の効率化
意思決定の効率化は、関連会社を設立する代表的なメリットです。組織が大きくなるほど、株主総会や取締役会で承認を得るのが難しくなります。意思決定のスピードダウンが起きれば、企業の競争力にも影響が出てくるでしょう。
そこで関連会社(子会社)を設立し、少人数の取締役が経営を担うことで、スピーディーな意思決定が可能になります。さらに別会社にして事業を切り分ければ事業売却も容易です。
後継者の育成
後継者の育成も大きなメリットです。関連会社の経営を後継者に任せることで、後継者の育成につながります。
後継者候補が複数存在する場合に、それぞれ別の会社を継がせることもできます。例えば後継者候補として複数人の親族がおり、それぞれ会社を継がせたいといったケースもあるでしょう。
上記の場合、関連会社を複数設立していれば、「親会社を子どもに継がせる」「関連会社を他の親族に継がせる」といった方法も可能です。
節税効果
関連会社を設立することで親会社の利益が分散され、節税効果につながるといったメリットも見逃せません。資本金額によっては、法人税や地方法人税、消耗品の軽減措置を受けられる可能性もあります。
事業の切り分けは節税効果だけではありません。リスク管理として関連会社を設立するケースもあります。例えば多くの投資が必要な部門を作る際に、親会社にそのまま設置するのではなく関連会社として設立すれば財務リスクを軽減できます。
関連会社設立のデメリット
関連会社設立にもいくつかのデメリットがあります。関連会社などが不祥事を起こすと、親会社を含めたグループ会社全体に影響を及ぼす可能性があることです。親会社が直接不祥事に関わっていなくても、結果として、経営に大きな影響を与えるリスクがあります。
さらに親会社の影響力が強すぎると、関連会社の経営能力が失われてしまい、親会社に依存してしまう可能性もあります。関連会社設立を検討している場合は、メリット・デメリットをよく整理しておくことが重要です。
関連会社の決算上の取扱い
関連会社や子会社がある場合は、親会社と一つの組織体としてみなし、連結決算を行う必要があります。ここでは主な会計処理や持ち分法適用会社、持ち分法と全部連結の違いを詳しく解説します。
関連会社や子会社の会計処理
関連会社や子会社がある場合は、連結決算で連結財務諸表を作成し、グループ会社全体の経営成績や財務状態を明確にしなければなりません。従来は、親会社のみの決算書(単独決算)で、グループ全体の経営成績・財務状況や、キャッシュフローを見ていました。
しかしこれでは関連会社や子会社を使った不正などもあり、会計の透明性が失われてしまいます。そこで連結財務諸表の作成が義務付けられるようになり、単独決算主義から連結決算重視の方向性に変わりました。
連結財務諸表では親会社と子会社間の取引は内部取引とされるため、より適切な経営状況の把握が可能になります。
持分法適用会社とは
持分法適用会社とは、連結財務諸表の作成に関して持分法の適用対象となる会社です。原則として、議決権所有比率20%以上かつ50%以下である会社を指します。
子会社の決算書を連結財務諸表に合算する際は、親会社との関係性に応じて各社を「連結子会社」「非連結子会社」「関連会社」に分ける必要があります。そして、それぞれに適用される決算方法によって親会社に連結させることが原則です。連結子会社は全部連結、非連結子会社と関連会社は、持分法がそれぞれ適用されます。
全部連結と持分法では、連結財務諸表の作成にあたって連結の処理が異なってきます。詳しい違いは次の項目で詳しく解説します。
持分法と全部連結の違い
持分法とは、親会社が関連会社などの持分法適用会社の資本と損益の中で、親会社に帰属する部分を連結決算に組み入れる方法です。全部連結とは異なり、財務諸表を全て合算する必要はなく、親会社に関連する部分のみ連結させます。
持分法のメリットは、全部連結に比べて会計処理がしやすい点です。全部連結の場合は、親会社と子会社の財務諸表を連結した上で、少数株主の持分を控除するなどの処理が必要になります。しかし持分法は、「投資有価証券」「持分法による投資損益」の2つの勘定科目を使って、親会社の財務諸表に反映させます。
なお持分法が適用される会社には、関連会社の他、親会社の支配が一時的または重要性の低い子会社(非連結子会社)もあります。
関連会社の会計処理
関連会社の会計処理には、主に以下のようなものがあります。
・株式の取得
・関連会社への販売
・当期の損益確定
・配当の受け取り
上記4つのシチュエーションでの、実際の仕訳方法を解説します。
株式の取得
まずは株式の取得に関する仕訳です。以下のシチュエーションを想定した仕訳方法を解説します。
・A社はB社の株式1,500株を1株あたり1,000円で取得した
・発行済み株式数5,000株
上記の場合は、株式の取得に関する仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 関連会社株式 | 1,500,000 |
| 貸方 | 現金 | 1,500,000 |
関連会社への販売
関連会社への販売もよく見られるケースです。以下のシチュエーションを想定した仕訳方法を解説します。
・A社はB社へ1個あたり1,000円、利益400円の商品を1,000個販売した
・しかし、B社からグループ外の会社への販売は行っていない
まずは、A社からB社へ商品を販売した際の仕訳です。
| 借方 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 貸方 | 売上高 | 1,000,000 |
ただしB社からグループ外の会社へは販売されていないため、持分30%に相当する利益を取り消し処理する必要があります。仕訳は以下のとおりです。利益は400×1,000=40万円であり、この30%である12万円を処理します。
| 借方 | 持分法による投資損益 | 120,000 |
| 貸方 | 関連会社株式 | 120,000 |
当期の損益確定
当期の損益確定をしたい場合の仕訳も重要です。以下のシチュエーションを想定した仕訳方法を解説します。
・B社の当期純利益は1,000万円で確定
ここでは、A社の持分30%分である、300万円を利益として計上します。仕訳方法は以下のとおりです。
| 借方 | 関連会社株式 | 3,000,000 |
| 貸方 | 持分法による投資損益 | 3,000,000 |
配当の受け取り
配当金を受け取った際の仕訳もあります。以下のようなシチュエーションを想定して仕訳をしてみましょう。
・A社はB社の株式1,500株を保有し、1株あたり100円の配当金を受け取った
仕訳方法は、以下のとおりです。
1.B社から配当金を受け取った際の仕訳
| 借方 | 現金 | 150,000 |
| 貸方 | 受取配当金 | 150,000 |
2.関連会社株式へ振替した際の仕訳
| 借方 | 現金 | 150,000 |
| 貸方 | 関連会社株式 | 150,000 |
3.持分法を適用した際の仕訳
持分法では、差を埋めるために以下の仕訳をします。
| 借方 | 受取配当金 | 150,000 |
| 貸方 | 関連会社株式 | 150,000 |
まとめ
関連会社とは、原則として親会社が株式を20%以上取得しており、経営上の影響力が強い会社のことです。関連会社や子会社などを保有する会社の場合、連結財務諸表を作成する必要があるため親会社の経理業務がやや煩雑になります。特に関係会社の規模が拡大しているような場合は、関係会社間の取引を専門に扱う担当者の配置が必要になるでしょう。
連結決算では、親会社と子会社の財務諸表を連結し、さらに少数株主の持分を控除しなければなりません。このような煩雑な業務に注力するためには、経理部門の業務効率化が求められます。コクヨの電子帳票配信システム『@Tovas』を導入すれば、帳票書類を電子化してWeb上で送付できます。また、必要に応じて郵送やFAXでの送付も可能です。さらに、送付した帳票類を電子帳簿保存法に対応した形で簡単に管理できるようになるため、経理業務を大幅に効率化できます。経理業務の効率化を目指している場合は、ぜひ導入をご検討ください。
@Tovasマーケティング担当(コクヨ株式会社)